フジテレビ系『酒のツマミになる話』が年内での終了を発表しました。発端は、10月24日(金)放送回が当日に再放送へ差し替えられたこと。フジテレビは「再生・改革の取り組みを進めている弊社の状況を鑑み」「社内連携に不十分な点があったため直前変更になった」と説明しましたが、決裁の実名・階層は示されず、番組のMC・千鳥の大悟さんは降板を表明。視聴者の前で胸中を語るという異例の展開になりました。
タイムラインでみる経緯
-
10月24日(金)
予告されていた“ハロウィン特別回”が当日に過去回へ差し替え。一部メディアは、大悟さんの「松本人志さんコスプレ」など“あるコスプレ”が局内で問題視されたため、と報じました(公式は内容に触れず)。 -
10月31日(金)
番組冒頭テロップで「年内終了」を正式発表。続けて大悟さんのVTRコメントが放送され、**「ノブと話し合って、やめまーす!」**などの趣旨で降板を伝達。放送中に当事者が直接説明する“異例さ”自体がニュースになりました。 -
同日
フジテレビは番組サイトで差し替え理由を「弊社の状況を鑑み」とし、社内連携不足が直前変更の一因になったと公表。降板申し出を受け、社内協議の結果「年内終了」と説明しました。
差し替えは誰の判断か――“現場”ではなく“上”の判断
フジテレビの公式説明は抽象的で、決裁者・部署は明らかにされていません。しかし複数の報道は、「局の上層部(幹部)やコンプライアンス部門」が放送見送りを決めた旨を伝えています。少なくとも制作現場の単独判断ではなかった可能性が高い。ここで問題なのは、「当日差し替え」という運用です。制作・編成・広報・スポンサー調整が複雑に絡む地上波で、当日変更は現場への負荷と損失が極めて大きい。それでもなお差し替えに踏み切った背景として、同局の“再生・改革”と称されるガバナンス硬直が影響したとの見立ても報じられました。
編集部注:フジテレビは2025年春、別件のコンプライアンス不祥事を受けた第三者調査報告書を公表しており、編成制作ラインの意思決定や人権感度、危機管理の不全を厳しく指摘されています。今回の差し替えは別件ですが、組織の意思決定の硬直という構図は重なって見えます。
大悟さんの“表明”は何を守ったか
10月31日の放送で大悟さんはVTRで降板を自ら伝えました。報道では、「面白くなければテレビじゃない」という趣旨のコメントも紹介されています。演者としての矜持と、視聴者への直接説明を選んだ点は評価すべきです。たとえ番組の継続を望む声が多くとも、**現場が最後に拠って立つのは“番組の理念”**です。不透明な差し替え運用が理念を損なうと判断したなら、降板=筋を通す姿勢は理解できます。
「制作会社」はどこか――制作と“制作協力”の整理
『酒のツマミになる話』はフジテレビ編成総局バラエティ制作局の制作で、吉本興業のプロデューサー(クレジット:宮下森資さん)が名を連ねてきた体制です。さらに技術協力としてニユーテレスなどが“番組づくり”を支えています。地上波バラエティの現実は、局制作 × 芸能事務所・制作プロ × 技術プロの共同作業。問題が起これば連携の目詰まりが即座に全体へ波及します。
要するに、「制作会社=フジテレビ(制作)」「制作協力=吉本興業」「技術協力=ニユーテレスほか」という構図。現場は“連帯責任”で動くのが通常で、当日差し替えは全ラインに痛手です。
大悟さんと制作サイドを擁護する理由
-
視聴者への説明責任を果たしたのは現場だった
当日の“テロップ+VTR”で直接説明したのは番組側。編成判断の透明化は本来、局の広報・経営ラインの役割です。現場に説明だけを背負わせる構図は不健全です。 -
企画の自由度は“事前審査”で担保すべき
コンプラやブランド毀損の懸念は収録前の段階で審査・調整するのが筋。当日差し替えは、制作・出演・スポンサー・視聴者のすべてに対するコストが最大化します。運用の失敗を現場の“攻め”のせいにするのは本末転倒です。 -
“コンプラ厳格化”は手段であって目的ではない
別件不祥事を受けた再発防止の徹底は当然ですが、“安全第一”が“挑戦排除”へ転化すれば、地上波の競争力は落ちます。理念(面白さ)と安全(法令・人権・品位)の両立こそ管理職の仕事です。 -
降板は“プロテスト”ではなく“理念の選択”
報道はしばしば「売れっ子の横暴」といったレッテルを貼りがちですが、当事者が理念を理由に現場を離れる自由も文化の健全性には不可欠です。**責められるべきは“ガバナンスの遅延と不透明”**であって、現場の理念表明ではありません。
フジテレビの説明はなぜ不十分に映るのか
フジテレビは公式に**「弊社の状況を鑑み」「連携に不十分」と語りました。しかし、具体的な審議プロセス(いつ・どの会議体で・誰が・何を根拠に)が明らかにされず、どの規程・基準が抵触の疑いだったのかも不明のまま。
これは同社が第三者調査報告書で指摘された、思い込みや狭い視野のまま意思決定が進みやすい構造と通底しています。「誰が」「何を」判断したのかを説明できない組織は、結果として現場にしわ寄せ**を生み、視聴者の信頼も毀損します。
7. 何が“起きていた”のか
-
制作サイドの目線
ハロウィン回という季節企画は、タレントのイメージや番組文脈を踏まえた**“攻め”の演出**。**安全確認(衣装・表現・権利・肖像の観点)**は通常、事前の社内審査で折り合いをつけて収録・編集に至ります。当日差し替えは、直前に“上振れ”たリスク判断があったか、連絡フローの破綻があった可能性が高い。 -
大悟さんの目線
“面白さの理念”と“視聴者への誠実さ”の両立を守るには、自らの降板で線を引くしかない――そういう倫理的決断だったのではないか。放送での直接説明は、その覚悟の表れです。 -
フジテレビの目線
社の再生プロセスを優先し、“誤射”を恐れる心理が働いた。だが当日運用の混乱は、視聴者・出演者・制作会社・スポンサーすべての信頼コストを増やした――そのことへの自省の言葉が、公式説明からは読み取りにくい。
“制作会社”は責められるべきか
責められるべきではありません。
理由は三つ。
① 体制上、最終放送可否の権限は局側にあります。制作協力・技術協力は品質と安全の担保を担いますが、オンエア判断の決裁者ではない。
② 当日差し替えが示すのは、連絡系統の不全と承認ゲートの設計ミスです。現場が事前に通した企画を土壇場で否決するなら、ルールが機能していない。
③ 番組の理念やブランドを守る声を、演者と制作が連携して表明した――これはむしろ文化防衛です。
今回の教訓――“攻め”と“安全”を両立させる運用へ
-
① 企画のレッドラインを“明文化”し、審査を前倒し
収録前に具体的基準と例外運用を共有。当日差し替えは最終手段に。 -
② 役員・局長級の決裁は“議事ログ化”し、説明責任を担保
誰が・いつ・何を根拠にを残すことが再発防止につながります。 -
③ 演者・制作・編成・広報・スポンサーの“同席レビュー”
波及影響の大きい回は合同レビューをルーティン化。直前の一存判断を避ける。 -
④ 視聴者説明は“局”が正面から
公式会見・FAQなどで具体を示す。現場に説明を丸投げしない。
結語――“守るべきもの”は何か
今回の一件で、現場(演者・制作)は視聴者に向き合い、理念を守ろうとしたのに対し、フジテレビの説明は抽象的で、運用の失敗を覆い隠す印象を与えました。地上波の矜持は、攻める企画と品位・人権を守る仕組みの高度な両立にあります。
攻めを止めるのではなく、止めずに済む仕組みを作る。
それができなければ、失われるのは“面白さ”だけでなく、視聴者の信頼そのものです。大悟さんと制作チームの**“前を向く”決断は、文化としてのテレビをもう一段強くするための痛みを伴うメッセージ**だった――のではないでしょうか。

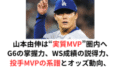
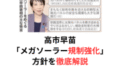
コメント