北海道・釧路湿原周辺で相次ぐメガソーラー計画に対し、アルピニストの野口健さんとタレントのつるの剛士さんが現地を視察し、自治体との意見交換や法整備の必要性を呼びかけました。お二人は再エネそのものを否定せず、「自然と調和しない大規模開発」を正すためのルール作りと、合意形成のプロセスを前に進めようとしています。本稿では、直近の動き、掲げる基本方針、提言の要点、期待される効果を整理し、あわせてネットの主な反応もまとめます。
直近の主な動き(時系列)
-
現地視察と発信
2025年10月初旬、野口健さんとつるの剛士さんは釧路湿原周辺の建設予定地を視察。希少生物の生息や景観・地盤への影響を懸念し、会見やSNSで問題提起しました。 -
自治体トップとの意見交換
視察後、釧路市長と面会し、「ノーモア・メガソーラー宣言」や条例制定など地域からの規制の発信が全国に波及することへの期待を表明しました。 -
SNSでの継続的な呼びかけ
野口さんは「全てのメガソーラーに反対ではない」としつつ、法令違反や地元の強い反対がある案件には歯止めが必要と投稿。つるのさんも「これは本当にエコなのか」という率直な疑問を投げかけ、議論を可視化しました。 -
社会的関心の拡大
釧路湿原周辺の計画をめぐるオンライン署名には著名人も賛同し、世論の後押しが広がっています。
お二人が示した「基本方針」
お二人の発言や行動から、一貫した方向性が読み取れます。
-
「再エネは必要、だからこそ“やり方”を正す」
日本の脱炭素に再エネは不可欠。ただし、湿原や原生林、希少生物の生息地と衝突する立地や、法令違反・ズサンな造成は認めないという立場です。野口さんの「全面反対ではない」という姿勢は、対立ではなく解決志向の議論に道を開いています。 -
「ルールと合意の再設計」
国の法整備の不足が自治体にしわ寄せされている現状を踏まえ、国レベルのルール整備+自治体条例を組み合わせ、**事前の合意形成(住民・専門家・自治体・事業者)**を制度に組み込むべきと呼びかけています。 -
「象徴案件から全国へ」
釧路湿原のような象徴的な案件で適正化の前例をつくり、全国の同種案件に波及させるという“ボトムアップ+トップダウン”の両面アプローチを志向しています。
具体的提言
お二人のメッセージを建設的な政策パッケージとして言語化すると、次のように整理できます。
立地・設計の「適地化」
-
屋根置き・遊休地・造成済み工業地など、自然価値の低い場所を優先。
-
湿地・保全林・希少生物の生息回廊は原則回避。
-
既設設備は**“リパワリング(高効率化)”**で出力増を図り、新規の自然改変を最小化。
手続の「可視化と合意形成」
-
初期段階の情報公開(配置図・排水計画・伐採量・土砂移動量・保全対策)。
-
外部専門家によるレビューと住民協議を義務化。
-
地域貢献計画(防災・生態系保全基金・景観協定)を契約に組み込む。
監督の「法整備と執行強化」
-
国の包括法で、森林法・自然公園法・文化財保護・鳥獣保護等との横断的審査を一本化。
-
違反時の是正命令・停止命令や**再生義務(原状回復基金の供託)**を制度化。
-
違反歴のある事業者への入札・認定制限を明確化。
エネルギー面の「現実解」
-
分散型電源×蓄電池で出力変動を抑制。
-
送電網整備と系統接続の優先順位を立地評価に反映。
-
地域の**レジリエンス(災害時電源)**を高める設計を誘導。
これらは再エネの推進力を落とさず、自然・暮らし・安全と調和させるための実務的な「線引き」です。お二人の行動が世論喚起とルール改善の両輪を回す“触媒”になっている点は、極めて建設的だと言えます。
なぜ「釧路」からなのか
釧路湿原はラムサール条約登録を持つ世界的な湿地で、タンチョウやワシ類など希少生物の生息地が重なります。短期間の造成で湿原や周辺に不可逆の影響が出る懸念が指摘され、“象徴案件”として社会的関心が高まったことが背景です。つるのさんの「本当にエコなのか」という問いは、“量の拡大”から“質の整合”へと議論を一段深めました。
「全面反対ではない」から生まれる接点
野口さんの「全てのメガソーラーに反対ではない」というスタンスは、事業者や行政との対話の余地を確保し、“適正化”という共通目標で接点をつくります。再エネ推進側にとっても、乱開発の負の外部性(土砂災害・景観破壊・地域対立)を減らすことは社会的受容性(Social License)を高め、結果として良い案件を通しやすくする利点があります。
全国への波及効果
-
自治体の動きが活発化:宣言・要綱・条例でゾーニングや手続きを明確化。
-
メディア露出で透明性向上:取材や番組化、SNS拡散で実態が可視化。
-
自然保護×再エネの“両立設計”が標準化:合意形成と外部監査を前提にする流れが定着。
-
象徴案件の「前例」が抑止力に:不用意な計画の“駆け込み”に歯止めがかかる。
ロードマップ
-
緊急対応:造成停止・現地調査・暫定ガイドライン/重要生息地の保全措置。
-
短期(~1年):自治体条例の整備/適地マップ(生態・地盤・流域)を公開/住民協議の標準モデル化。
-
中期(~3年):国の横断法制化/再エネ評価と生態影響の一体審査導入/原状回復基金の義務化。
-
長期:屋根置き・既開発地優先+リパワリングの主流化/地域レジリエンスを高める分散型×蓄電の標準化。
お二人の発信が持つ価値
-
“自然保護”と“エネルギー転換”の二項対立を超える視点を提供。
-
象徴案件での社会的合意づくりを促進。
-
法整備と現場改善の橋渡し役として、具体のアクションへと議論を動かす。
この解決志向のスタンスは、今後の日本の再エネ推進に欠かせない“質”の議論を加速させます。
ネットの主な反応
-
「再エネは必要。だからこそ湿原は外すべき」
-
「“エコのための破壊”は本末転倒」
-
「屋根・遊休地・駐車場からやってほしい」
-
「条例でゾーニングして線引きを」
-
「視察と発信に感謝。議論が進んだ」
-
「行政の執行力が弱い。罰則強化を」
-
「地元の声を最初からテーブルに」
-
「希少生物の回廊を壊さない配置を」
-
「“全面反対じゃない”という姿勢が現実的」
-
「短期のFIT収益だけ見る計画はNO」
-
「原状回復の基金を義務化して」
-
「土砂流出・洪水リスクの評価を厳格に」
-
「景観協定を結んで緩衝帯を確保」
-
「送電網の制約も最初に説明して」
-
「地域の非常用電源として機能させて」
-
「違反事業者は参入制限を」
-
「住民説明は“事後報告”でなく“共創”に」
-
「屋根置き+蓄電池の補助を厚く」
-
「既設の高効率化(リパワリング)を優先」
-
「自然公園法や鳥獣保護と整合を」
-
「開発のスピードより質を」
-
「地盤が弱い土地は原則回避」
-
「施工・維持管理の透明化を」
-
「自治体間で前例・知見を共有して」
-
「“ノーモア宣言”は全国でできる」
-
「再エネは嫌いじゃない、やり方を直せ」
-
「外部専門家レビューを常設に」
-
「地元雇用と自然保全を両立して」
-
「“とにかく早く大量に”の時代は終わった」
-
「この議論を次世代の環境教育につなげたい」
10. まとめ
野口健さんとつるの剛士さんの行動は、再エネ推進の“量”から“質”への転換を象徴しています。釧路湿原という象徴的な場で、「どこに・どう造るか」の原則を社会に示し、国の法整備と自治体のルールづくりを前に進める。
お二人は“反対か賛成か”の単純な対立を超え、解決の設計図を描くリーダーシップを発揮しています。今後、象徴案件の改善→制度化→全国展開という流れが定着すれば、自然とエネルギーの両立は十分に可能です。私たち一人ひとりが情報公開と合意形成に参加する姿勢を持つことこそ、このポジティブな変化を持続させる原動力になります。
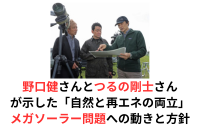


コメント