熊出没は「感覚」ではなく、数字で見ても“非常事態”です
まず現状を数字で押さえます。
-
環境省などの集計によると、2023年度は熊による人身被害が統計開始以来最多クラス。2023年4〜11月で193件・212人被害・死者6人というデータが出ています。
-
2024年度も高水準が続き、2025年はさらに深刻化。報道ベースでは**2025年は4月以降で100人超負傷・10人以上死亡(11月時点)**とされ、2023年を上回るペースです。
-
秋田・岩手・北海道などでは、住宅街・学校周辺・スーパー駐車場・駅近くまでクマが出没し、自衛隊派遣やイベント中止にまで発展しています。
つまり今は、
「たまに山奥で事故がある」ではなく
「人の生活圏全体がクマとの衝突リスクにさらされている」
と見なさなければいけない段階です。
なぜここまで増えているのか:複合要因を冷静に見る
個体数回復と分布拡大
長期的には保護政策などもあり、ツキノワグマ・ヒグマの分布域・個体数は回復傾向とされる地域が増えています。これは本来望ましいことですが、「管理」とセットでやらなければ人との衝突が増えるのは当然です。
里山放棄・過疎化で「境界」が消えた
-
農林業の縮小・高齢化で、山際の畑や薪山が放置される。
-
人の気配が薄くなり、クマから見れば「静かでエサもある安全地帯」に。
-
その延長で、集落や住宅地に入っても追われにくく、人慣れが進みます。
エサ不足と気候要因
-
ドングリ・ブナ・ナラなど堅果類の凶作や偏り、
-
暖冬・季節変動により冬眠時期がズレることなどが重なり、
山のエサが不安定 → 人里の果樹・農作物・生ゴミへ流入という構図が繰り返し指摘されています。
ソーラーパネルを含む乱暴な開発
-
一部のメガソーラー事業では、山林大規模伐採→地盤・植生・動物の移動ルートを破壊しているケースがあります。
-
森林分断や斜面崩壊は、クマを含む野生動物の生息環境に影響し、人里へ出る要因の一部になり得ます。
-
政府も近年の方針で「自然環境と調和しない乱開発型再エネ」への懸念を示しており、本来は既存施設・荒廃地優先が筋です。
「ソーラーがすべて悪い」とまでは言えませんが、
“安易な山林切り売り”が生態系と人間生活の両方にツケを回しているのは事実です。
極端な「熊を殺すな」論への反論:人命軽視は保護でもなんでもありません
ここで一度線を引きます。
-
むやみに撃ちまくれ、という発想は論外です。
-
同時に、「住宅街に出てきたクマも一頭も殺すな」「人間が悪い」で片付けるのも、やはり論外です。
特に問題なのは、
-
危険個体への駆除を“感情論だけ”で否定する言説
-
現場のハンター・自治体職員を攻撃し、萎縮させる行為
-
代替策(費用・人員含め)を何も提示しないまま、「かわいそう」の一点張り
です。
人里・通学路・学校・駅前に繰り返し出没し、人を襲うリスクの高い個体については、
人命と生活を守るための駆除はやむを得ない措置です。
これを否定して事故が増えれば、最終的には「全部駆除しろ」という極端な反動を招き、クマ保護にとっても逆効果になります。
本当にクマを守りたいなら、
「危険個体は迷わず排除しつつ、生息域保全と人側の管理を強化する」という現実的ラインを取るべきです。
狩猟免許と銃所持許可:撃つ人だけが“リスク全部押し付け”の現状
熊対策の最前線にいるのは、
-
都道府県知事の狩猟免許
-
公安委員会の銃砲所持許可
-
自治体の委嘱を受けた有害鳥獣駆除従事者(多くは猟友会)
を持つ、ごく限られた人たちです。
ところが近年、この人たちが「撃ったら人生終わりかねない」と感じる出来事が続いています。
砂川のライセンス取消事件
-
北海道砂川市でヒグマ駆除に出動したベテランハンターが、要請に応じて発砲・駆除。
-
のちに「住宅等への危険性」を理由に銃所持許可を取り消される処分。
-
この取消を巡る訴訟で、高裁が処分適法と判断したことで、ハンター側に強い萎縮が広がったと報じられています。
要するに、
自治体や警察の要請に応じて命懸けで動いても、
後から「危険だった」と言われれば免許を失いかねない
という前例ができたわけです。
「危険な撃ち方」に一定の歯止めが必要なのは当然ですが、
適正な駆除まで一律に“自己責任”で切り捨てるような運用では、誰も前線に立ちたがらなくなるのは当然です。
議員によるハンター軽視:積丹町の騒動が象徴するもの
北海道積丹町では、
-
町議会副議長の自宅近くでクマが捕獲された際、
-
安全確保のため距離を取るよう求めた猟友会側に対し、
-
「誰に向かって言っている」「こんなに人はいらない、金目当てだろ」等の暴言や、
-
駆除予算や猟友会活動を示唆する発言があったと猟友会側が主張し、
-
-
その後、猟友会が出動を拒否する事態に発展したと報じられています。
副議長側は一部内容を否定しているものの、この騒動が突きつけたのは、
「命懸けで前線に立つ人を、政治家が理解せず冷遇・恫喝すらする」構図
です。
砂川の免許取消と積丹の騒動を合わせると、
-
撃てば法的リスク
-
出れば政治的・世論的リスク
-
報酬は高くない、装備も自己負担が多い
-
ハンター人口は高齢化で減少
という**「やったら負け」環境**になっており、
結果として一番危険な目にあうのは、一般住民と子どもたちです。
国の対応:ルール緩和は始まったが、まだ片手落ちです
出没と被害の急増を受け、日本政府もようやく重い腰を上げ始めています。
-
2024年末〜2025年にかけて、市街地などでの“緊急的な熊射殺”を自治体判断で行いやすくする法改正・運用緩和。
-
2025年秋には、記録的被害を受けて自衛隊の協力投入や、警察のライフル活用検討なども公表されました。
しかし、
-
駆除現場の判断に対する免許取消リスクの明確なセーフティ
-
猟友会・ハンターへの報酬・保険・装備・訓練支援
-
無責任な圧力をかける政治家へのチェック
といった点は、まだ不十分です。
「撃ちやすくしたからあとはよろしく」ではなく、
「適正に撃った人は守る」「現場へのリスペクトを制度で担保する」ことが不可欠です。
一般の私たちが知っておくべき「遭遇時行動」と「クマよけ」
ここからは実務です。これも記事として重要なパートなので整理します。
事前にやること
-
自治体の「クマ出没情報」「防災メール」をチェックします。
-
早朝・夕方・薄暗い沢沿いや藪を一人で歩かないようにします。
-
クマ鈴・ラジオ・会話などで「人の存在」を知らせます。
-
家の周りの柿・栗・生ゴミ・ペットフードなどエサになるものを放置しないようにします。
遭遇したら
-
走って逃げない(背中を見せない)。
-
クマを見ながらゆっくり後ずさりし、距離を取ります。
-
大声でわめいて挑発しない(状況により低めの声で存在を知らせる)。
-
子グマを見ても絶対近づかない(母グマが一番危険)。
-
万一突進してきた場合、クマ撃退スプレーがあれば顔面に噴射(事前訓練が前提)。
クマよけグッズ
-
クマ鈴・ラジオ:不意の遭遇を避ける意味で基本装備。
-
クマ撃退スプレー:正しい製品と使い方なら高い有効性が確認されています。
-
電気柵:農地・家周りを守るなら極めて有効。補助金も要チェック。
-
ライト・防犯ブザー:夜間の市街地出没に対して一定の効果。
「絶対安全」な道具はありませんが、何もしないよりは格段にリスクを下げられます。
これから必要なこと:感情論ではなく「線引き」と「現場支援」を
最後に、この一連の熊騒動をどう整理すべきかまとめます。
-
熊出没の増加は構造問題
-
個体数回復、里山放棄、エサ不足、乱暴な開発、人慣れ――
-
「熊が悪い」「人間が悪い」と単純化しても解決しません。
-
-
人命最優先は譲れない
-
住宅街・学校・生活圏に繰り返し出るクマや、人を襲った個体は、ためらわず駆除するルールが必要です。
-
それを実行する人を叩くのは筋違いです。
-
-
ハンターと現場へのリスペクトと保護
-
駆除要請に応じた者が、後から免許取消リスクや政治的圧力に晒される現状は異常です。
-
法的な「セーフティ」と、十分な報酬・装備・保険・訓練支援が不可欠です。
-
-
極端な「一切殺すな」論は結果的にクマも守れない
-
危険個体の排除が遅れ悲惨な事故が増えれば、「全部駆除しろ」という逆の極論を強めるだけです。
-
冷静なゾーニング(保全エリアと人の生活圏の線引き)が、長期的な保全にもつながります。
-
-
一人ひとりが“クマがいる前提”にアップデートする
-
出没情報の確認、エサ源管理、山や河川敷での行動に気をつけることは、もう「山奥の人だけの話」ではありません。
-
感情だけで「かわいそう/ひどい」と叫ぶ段階は終わっています。
人命を守りつつ、前線に立つ人を守り、必要なクマは守る。そのための制度・運用・世論をどう作るか――そこに議論を集中させるべきだと考えます。


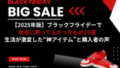
コメント