X上で拡散している「埼玉の家屋が解体途中で半壊状態のまま放置され、近隣が不安視している」件について、現地確認の報告が出ており、AI画像ではなく実在する状況だとされています。本稿では、何が法令・安全面でアウト(NG)になり得るのか、なぜ“警察がすぐ取り締まらない”ように見えるのか、そして住民が今すぐ取れる現実的なアクションを、制度と実務の順に整理します。
まず押さえるべき全体像:この種の案件は「行政法+労働安全+環境」の所管分担
解体現場の適正・違法の判断は、ざっくり**(A)建設リサイクル法・建築基準法などの“行政法”、(B)労働安全衛生(労基署)、(C)石綿(アスベスト)など環境規制**、**(D)道路使用(警察)**の4レーンでみます。
-
建設リサイクル法:延床80㎡以上の解体は着工7日前までに発注者が届出が必要。契約書には分別解体や再資源化先等の明記義務があります(自治体の手引で明記)。
-
石綿(アスベスト):2022年以降、すべての解体・改修工事で事前調査が義務化。一定規模以上は基準局・自治体への電子報告が必要で、調査は有資格者が原則です。
-
労働安全衛生:足場・養生・墜落防止など現場の安全確保は労基署の所掌。急迫の危険があれば監督官が“その場で使用停止命令”を出せる権限があります。
-
道路使用(警察):公道に資材・重機がはみ出す等は道路交通法の道路使用許可の対象。道路管理者の道路占用許可とは別枠で、必要に応じ警察対応となります。
結論:「誰が何を取り締まるか」は分野ごとに違うため、警察だけ見て「動かない」と断じると全体を見誤ります。
この現場で“NGになり得る”チェックポイント(住民目線の早見表)
現場の写真・動画から読み取れる典型的な赤信号は次のとおりです。該当が多いほど、行政・労基署への通報価値が高まります。
-
養生・仮囲い・足場が乏しい/無い:粉じん・落下物対策としての足場+防音/防塵シートは基本中の基本。周囲が生活道路なら誘導員配置や警備計画も通常必要です(労安の観点)。
-
解体の手順が逆(下から先に抜く等):上部から順序良く、残存躯体は支保工で安定確保が鉄則。**1階が抜け、2階が“宙づり”**のような構図は倒壊リスクの典型。
-
アスベストの疑いに対する養生・湿潤化の不備:事前調査と報告が義務化され、飛散防止が必須。見た目で即断できなくても、調査済み掲示や手順が見えないのは強い違和感ポイント。
-
届出・許可の体裁:延床80㎡以上の解体なら建リ法の届出が前提。さらに騒音・振動の“特定建設作業”や道路使用許可の掲示が見当たらない場合は要確認。
「なぜ警察は取り締まらないの?」に対する制度的な答え
3-1 民事・行政分野は警察の直轄ではない
警察の本分は刑事事件の捜査・交通安全・治安維持で、建築・解体の適法性そのものは建築主事・特定行政庁(建築基準法)、労基署(労安法)、自治体の環境部局(大防法・石綿)等の行政所管です。民事不介入の原則もあり、当事者間の契約・工期トラブルに直接介入はできません。ただし、人身危険・道路交通の危険があれば警察対応の余地はあります。
3-2 現場停止は労基署の強い権限が軸
労働基準監督官は、急迫の危険があれば現場で使用停止命令を即時に出せる法的権限を持ちます。危険足場や墜落リスク、重機の不適切運用など**“労働者の生命に直結”**する態様は、警察ではなく労基署が止めるのが筋です。
3-3 建築基準法は段階的な措置(指導→勧告→命令→代執行)
危険建築物/違反建築物に対しては、特定行政庁が指導・勧告・命令を積み上げ、最終的に代執行(行政代執行法)という流れ。すぐに重機が来て撤去…ではなく**“適正手続”が必須**のため、**外からは“動きが遅い”**ように見えるのです。
3-4 道路上の危険や無許可使用は警察所管
資材・廃材が公道にせり出す、交通を妨げる、道路使用許可が疑わしい――こうした交通危険は**警察(交通)**の出番。**道路使用許可(警察)と道路占用許可(道路管理者)**は別物で、双方が必要な場合があります。
なぜ“その場で”警察が動かないのか――所管の壁を甘えにしない
一般に、**現場停止の即時権限は労基署(労働基準監督官)**にあり、建築物の是正・命令は特定行政庁(建築指導)、**公道の危険は警察(交通・道路使用)**が軸です。所管が分かれるのは制度上の事実ですが、それを理由に“動いているのか分からない”状態を放置することは許されません。
制度の分担自体は正しい。問題は、「分担されていること」しか伝えていない点です。市民が知りたいのは、“誰が・何を・いつまでに”やるのかです。
司法手続への疑念をどう解消するか――「平等適用」の検証可能性
不起訴・起訴は個別事情の塊であり、外からは分かりづらい。それが**“属性によって緩いのでは”**という疑念の温床になります。ここで必要なのは、人を標的にする言説ではなく、プロセスの検証可能性です。
提言
-
統計の分解と第三者監査
-
事件類型別に、検挙→送致→起訴→有罪のプロセス別統計を年次で公開。
-
属性別の差異を論じる前に、まず**行為の態様(危険度・結果・過失の程度)**で層別化し、同種事案の処理一貫性を監査する。
-
-
不起訴の理由分類の詳細化
-
形式的な「嫌疑不十分」だけで終わらせず、証拠の何が足りなかったのか、再発防止上の示唆を含むサマリー公開を制度化。
-
-
迅速な保全命令の運用徹底
-
危険建築・危険作業態様に対し、行政命令→不履行→代執行の時限フローを明確化。司法救済手続との整合を事前に示す。
-
ここまでやって初めて、市民は「等しく厳正に処理されている」と納得できます。
「強い行政」を邪魔しているもの――説明と責任の“宙ぶらりん”
-
曖昧な現地掲示:届出・許可・責任者・緊急連絡先の掲示が不完全だと、責任の所在がぼやける。
-
一体点検の欠如:建築・労安・環境・警察の同時臨場が仕組み化されておらず、是正命令の連動が弱い。
-
罰の周知不足:命令違反・無届・飛散等の行政処分・刑事罰の実例が周知されず、抑止力になっていない。
行政が“遅く見える”理由:適正手続と権限配分
-
財産権との衝突
建物は所有者の財産。強制的措置には命令→不履行→代執行といった段階と要件が必要です(建築基準法9条・10条、行政代執行法)。 -
事実認定に時間
届出漏れ、アスベスト、契約紛争、産廃の去就、道路占用の関係…複合要因で止まっていることが少なくありません。 -
“誰の所管か”を仕分ける必要
危険の態様に応じて、建築指導課/労基署/環境部局/警察へバトンを渡す作業が入るため、外形上は緩慢に映ることがあります。
住民が“今すぐ”できる具体アクション
-
危険の差し迫り度が高い(倒壊・落下物・通行人危険)
→ 110番/119番で緊急通報。道路上の危険は警察交通へも明確に伝える。 -
労働者安全や足場・墜落防止が粗い
→ 所管の労働基準監督署へ。急迫危険時は現場停止命令の権限あり。 -
届出・解体手順・危険建築の疑い
→ 市の建築指導課/特定行政庁(さいたま市等)へ建リ法の届出状況と現場指導を照会。 -
アスベストの疑い・粉じん
→ 自治体の大気(環境)部局に事前調査・報告の有無と飛散防止の指導確認。 -
道路使用・占用の疑い
→ 所轄警察署(交通)と道路管理者の双方に連絡。許可の有無を確認。
コツ:日時入りの写真・動画、粉じんや通行妨害の状況、危険の位置関係(道路・学校・横断歩道等)を添えて複数窓口に並行照会すると動きが早くなります。
「何が起きれば“刑事”になる?」の境目
-
人身事故(倒壊・落下物でけが人)、過失致傷/業務上過失致傷に発展
-
道路交通法違反(無許可使用で重大な危険発生)
-
労安法違反の重大・悪質事案(是正せず危険状態を継続)→ 送検(労基署経由)
-
大気汚染防止法・石綿関連違反で刑事告発に至るケースも
これらは**警察(または労基署→検察)**の領域になり得ますが、まずは行政指導→命令を経るのが一般的です。
“半壊のまま止まる”よくある要因
-
届出やアスベスト手続の不備→ 行政が停止・是正指導
-
想定外の構造不安(支保工の再設計待ち)
-
元請の資金繰り/契約紛争
-
産廃の受け入れ・運搬調整
-
道路許可の取り直し
結果として**「見た目は危険そうなのに何も進んでいない」時間帯が発生します。そこを行政・労基署・警察の適切な窓口に具体情報で“押す”**のが近道です。
まとめ:感情ではなく“所管と法令”で押す
-
NGの核は、手順(上→下/支保工)・足場養生・アスベスト対策・届出/許可の4点。
-
警察が“動かない”ように見える理由は、行政分野の所管だから。急迫の危険・交通危険は警察、現場停止は労基署が強い。

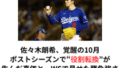

コメント