いま何が起きているのか
自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、臨時国会で首相指名・組閣に向けて動いています。高市氏は安全保障・改憲で保守色が強く、市場は財政出動継続と防衛関連の追い風を織り込み上昇しました。一方で、与党(自民+公明)は衆参とも単独では過半数に届かず、連立枠組みの再設計や**野党との「部分連合」**が不可避というのが足元の前提です。
「数」の現実:連立を考える前に、現在の議席状況
まずは国会の“算術”です。ここを押さえると、取り得る連立パターンが自然に絞られてまいります。
-
衆議院(定数465)
令和7年(2025年)9月末時点の会派別では、自民196、公明24。野党側は立民148、日本維新35、国民民主27などで、与党220 vs 過半数ライン233という不足が続いています。つまり、自公だけでは衆議院の過半数に届きません。 -
参議院(定数248)
直近の参院選を経て、自民100、公明21。両党合計121で、こちらも過半数125に届きません。
この「数」の制約から、自公を軸に“第三パートナー”を加えるか、自公を解消して新たな連立軸をつくるか、あるいは少数与党のまま“法案ごとに相手を替える”――いずれかの選択が避けられない状況です。
自公関係の現在地:公明党の“条件”と高市政権のレッドライン
公明党は高市氏の就任直後から、**支持層の不安に直結する論点(靖国参拝、歴史認識、外国人政策等)**について懸念を直接伝え、「懸念が解消されない場合は連立は組めない」と明言しています。これは交渉上の“牽制球”の側面もありますが、公明の基盤や外交配慮を考えると軽くは扱えません。
一方の高市氏は国防強化・経済再生(アベノミクス的運営)・規制改革に力点を置く姿勢を鮮明にしており、「保守色の強さ」×「大胆な財政・成長志向」が新政権のシグナルです。この政策色の差が、自公再合意の条件設定を難しくしている構図です。
シナリオ比較:解消 or 堅持 or 拡張か(実現性・政策親和性・議席算術)
シナリオA:自公を維持しつつ、**「部分連合」**で積み増す(最有力)
-
中身:自公の基本合意を再確認し、国民民主や日本維新と「法案単位」または限定テーマで協力。補正予算・経済対策・少子化財源・地方活性化などから着手。
-
利点:
① 衆参とも“与党の芯”を残せる/② 予算や税制など可決の見通しが立ちやすい/③ 地方選挙の**選挙区調整(特に都市部)**で公明の動員力を引き続き期待できる。 -
ハードル:
① 公明の条件(靖国・人権・移民・教育など)と高市カラーの折衝/② 参院でも「数合わせ」の相手を法案ごとに付け替える運営コスト。 -
実現性:高。公明は「政策協議は続ける」立場を取っており、当面の国会運営は**“自公+部分連合”**で走る可能性が一番高いと見ます。
シナリオB:自公を解消し、自民+日本維新+国民民主の“改革保守連立”
-
中身:自民(196)+維新(35)+国民(27)=258で衆院は安定多数。参院も自民(100)+維新(19)+国民(25)で144前後となり、法案処理は十分可能。
-
利点:
① 高市政権の安保・改憲・規制改革に親和的/② 道州制・地方分権・教育改革などで維新と政策接点が多い/③ ガソリン税・年収の壁など可処分所得を増やす系は国民民主が重視。 -
ハードル:
① 維新と国民民主の双方に配慮が必要(閣僚配分・重点政策の順序)/② 公明の地盤(都市部小選挙区)との選挙区再編で摩擦必至/③ 国会外・外交面での“急進色”への反発管理。 -
実現性:中。維新・国民は交渉に前向きな発言が相次ぐ一方で、「民意に反しない形」「政策履行の確約」を強く求めており、合意形成の作法が鍵です。
シナリオC:自民+国民民主の“中道路線”中心で、公明や維新は案件ごとに巻き込む
-
中身:衆院は196+27=223で単独過半数に届かないため、法案ごとに**公明(24)または維新(35)**を都度取り込み。
-
利点:
① 公明との全面決裂を避けつつ、家計減税・賃上げ促進などで国民民主と歩調を合わせやすい。 -
ハードル:
① 常に**「あと10票〜数十票」**を積み上げる政権運営の不安定さ/② 参院でも同様の都度交渉が必要。 -
実現性:中。当面の臨時国会・補正成立までは現実解だが、中期の改憲・安保立法には推進力が足りません。
シナリオD:自公を継続したまま、自公+維新で“保守大連立”(公明は残留)
-
中身:衆院196+24+35=255、参院も100+21+19=140程度で強固。
-
利点:
① 改革と安定の両取り/② 経済・地方分権・デジタル・教育で推進力。 -
ハードル:
① 安保・改憲で公明と維新の**“振れ幅”を同居**させる難度が高い/② ポスト配分・選挙協力の整理が複雑。 -
実現性:中低。三者の「譲れない一線」がぶつかりやすく、緻密な政策合意書が前提となります。
連立解消の可能性は?
短期(臨時国会〜補正成立まで、10〜12月)では、「自公の“完全解消”は中低確率」と見ます。理由はシンプルで、①補正・税制・人事など時間制約のきつい案件が目白押し、②都市部の選挙区での相互乗り入れを今すぐ白紙化すると次の国政・地方選で自民が痛手、③公明も協議継続を明言しているからです。一方で、公明側の懸念事項に象徴的な“踏み絵”(首相の靖国対応や人権・教育政策の文言修正など)が出れば、**年明け以降に「自公枠の見直し」**へ振れる余地は残ります。
キープレイヤー別の“着地点”
-
公明党:「支持層の安心」が最優先。歴史認識・人権・外国人との共生で閣議了解の文言や首相の行動指針に“安全柵”を求めるのが基本線です。交通・住宅・子育て支援などで成果獲得を急ぎます。
-
日本維新の会:規制改革・地方分権・教育は高市政権と親和性。連立に入るなら改革ドライブを強く要求。番組発言では「臨時国会前の大合意は難しい」と慎重姿勢も示しています。
-
国民民主党:可処分所得を増やす政策(年収の壁、ガソリン税の暫定税率など)の履行確約が鍵。クリアされれば連携の間口は広がる、と受け止められます。
高市政権がとると見られる当面の運営術(ロードマップ)
-
臨時国会(10月中旬見込み)での首相指名・組閣確定
→ 初閣僚人事は「経験重視」で内政・外交の信頼感を演出。市場には財政・成長シグナルを継続。 -
補正予算と物価・賃上げパッケージ
→ 公明・国民・維新が「乗りやすい」家計支援・生産性投資から通す設計。 -
自公“基本合意文書”の更新/注釈付け
→ 公明のレッドラインに配慮しつつ、安保・経済安保は言い回しで合意幅を確保。 -
改憲・安保・教育の“順序入れ替え”
→ 改憲は国会発議のメド・国民投票戦略を“次段”。まずは教育DX・医薬品政策・防災予算など、合意を作りやすい分野から実績化。 -
年末〜通常国会に向けた「連立のかたち」最終判断
→ 自公継続+部分連合を軸に、維新/国民との限定テーマ連立もオプション化。大きな外交イベントや景気局面の変化が決定打になります。
結論:解消は“選べるが、焦点はそこではない”
-
結論①:短期は「自公を土台」に運営する可能性が高いです。補正と税制、当面の物価対応を優先し、国民民主・維新との部分連合で厚みをつけるのが現実解です。
-
結論②:中期は「三者併存」か「改革保守連立」か。公明の条件が飲めない場合、自民+維新+国民という**“改革保守”型の新連立**に舵を切る選択肢が浮上します。数の上でも参衆ともに安定。
-
結論③:いずれにせよ、**カギは“数”より“設計図”**です。①何を先に通すか(優先順位)、②どの党にどの成果を割り当てるか(成果の見せ場)、③支持層が許容できる文言の落としどころ(レッドライン管理)――この3点の「職人芸」が、解消か継続かを超えて新政権の命運を左右します。
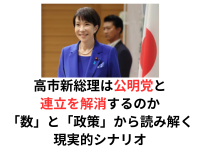
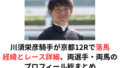

コメント