2025年のロサンゼルス・ドジャースにとって、佐々木朗希は「シーズン途中の計算外」から「10月の生命線」へと評価を一変させた投手でした。先発としてつまずき、長い離脱を挟みながらも、復帰後に救援転向。以降は高難度の場面を連続で火消しし、ポストシーズン9登板、10.2回、0.84という圧巻の数字(セーブ3)を残しました。ワールドシリーズ(WS)でも2試合で無失点と、舞台が上がるほど集中力を高める“ビッグゲーム体質”を証明しています。
レギュラーシーズンの出発点:先発での試行錯誤と負傷、そして役割転換
MLB一年目のレギュラーシーズンは10試合(先発8)36.1回、1勝1敗、防御率4.46、WHIP1.43。特に春先は制球面の波が大きく、四球が先行するイニングも目立ちました。5月中旬に右肩のインピンジメントで離脱し、夏場はリハビリに専念。9月24日に60日ILから復帰し、以後はブルペン起用へと方針を切り替えます。チームが地区優勝へ詰めの段階にあったこと、救援陣が不安定だったことが背景にあり、ロバーツ監督も「まずはブルペンで戦力化」を明言。復帰直後の登板では1回を完璧投球で終えるなど、救援適性を早々に示しました。
復帰の決断はチーム事情とも合致していました。ドジャースは9月時点で救援防御率が悪化し、“後ろ”の強化が急務。そこで「100mphの速球+落差の大きいスプリット」を短いスパンで解き放つ運用へ。結果的に、この役割転換がポストシーズン大躍進の伏線になりました。
ポストシーズン総括:9登板10.2回0.84、セーブ3——「最小失点で流れを渡さない」投球
ポストシーズンでは、9登板で10.2回を投げ自責1、防御率0.84、被打率.167台、セーブ3という“後ろの切り札”にふさわしい数字。リード時も同点時も投入可能なユーティリティ性を示し、1点差・走者有りなど痺れるタフ局面で連投でもパフォーマンスが落ちませんでした。**「先発型のスタミナ×クローザーの瞬発力」**というハイブリッドな強みが、最短距離で開花した格好です。
ラウンド別のハイライト
ワイルドカード(対レッズ)
初のメジャー・ポストシーズンで第2戦の9回をわずか12球前後の“パーフェクト締め”。球速は最速101.4mphを計測し、攻略の糸口を一切与えずにシリーズスイープを完成。ここで**「短いイニングでの最高到達点」**というブルペン適性を、全米に印象付けました。
NLDS(対フィリーズ)
第1戦は大谷翔平の先発勝利→佐々木がMLB初セーブという「日本人コンビでの勝ち・セーブ」史上初の偉業達成。第4戦では3回連続パーフェクトで突破口を与えず、接戦の延長戦勝利を呼び込みました。**“勝負所で空気を変える”**投球が、このシリーズで完全に定着します。
NLCS(対ブルワーズ)
第1戦で一度つまずくも(2/3回1失点)、第3戦でセーブを挙げて即座にリカバー。シリーズ終盤には**“とどめの最終回”を任される存在**となり、ドジャースのリーグ連覇に直結するクロージングを務めました。失敗からすぐ修正して帳尻を合わせた点は、短期決戦の評価を高める重要ファクターでした。
ワールドシリーズ(対ブルージェイズ)
Game3(18回の死闘)では1.2回を無失点。2つの走者を抱えた継投をゼロで切り抜け、超ロングゲームの勝利へ繋ぐ橋渡し役を成功させます。Game6では8回のピンチを凌ぎ、9回先頭を死球で出しつつも無失点で凌いで1点差勝利の土台を作りました(最終的なセーブはグラスノー)。WS通算では2登板2.2回、被安打3、無失点。雑音が最大化する舞台で、**「ゼロで帰ってくる」**という救援の原理原則を遂行した点が何よりも価値です。
なぜ10月の佐々木は強かったのか——“先発の作法”を携えたクローザー的運用
-
配球の引き出し
先発として培った直球ゾーン使いの幅とスプリットの見せ球/決め球の二段運用。救援では1巡勝負のため、直球で投げミスしてもスプリットで回収できる構図が明確になり、走者を背負ってからの投球設計に余白が生まれました。 -
メンタル面の伸長
春先の不振と長期離脱を経たことで、“結果以外のコントロール”(間の取り方、呼吸、テンポ)に意識が向き、失敗→即修正の回路が短期決戦に最適化。NLCS初戦の躓き直後にセーブで取り返した一連の過程は、**レジリエンス(回復力)**の高さを象徴します。 -
役割転換の決断と現場適応
チーム事情(救援の不安)と選手特性(球威・決め球)を現実主義でマッチングさせた現場の判断が的中。転向の道程を追ったレポートでも、**「抑え固定ではないが、最終回を任せ得るカード」として扱う運用思想が語られており、まさに“勝つための柔軟性”**が奏功したといえます。
メディア/周囲の評価の変化:未知数→“10月のキーマン”
シーズン中盤までは「ルーキー、先発、肩不安」という不確定要素から復帰も不透明と見られていました。ところが、終盤のブルペン転向→PSでの連続好投で、論調は**「ドジャースのシーズンを救った起点」「10月のキーマン」へ。米メディアでも“先発→クローザー的役割”の成功例として取り上げられ、セーブ3・防御率0点台という実績が、「来季の起用幅を広げる」**との見立てを後押ししています。
さらにNLDS第1戦の“日本人勝ち&セーブ”や第4戦の完全リリーフは、日本球界からの移籍1年目としてのニュースバリューも大きく、日米双方でポジティブに報じられました。**「舞台が大きいほど強い」**というレッテルは、WSの無失点リリーフで決定的になったと言ってよいでしょう。
ワールドシリーズという究極の検証台で示した“ゼロの重み”
WSのGame3は延長18回という異常事態。継投総動員の中で1.2回をゼロに抑え、走者を抱えた非日常の状況でも球威・球質を維持。Game6では、先頭打者への死球や**二塁打性の打球がフェンス根元に挟まる“珍事”など混乱の中でも、最終的に1点も与えない集中力を見せました。数字以上に「覚悟のゼロ」が鮮烈で、“結果で語る救援”**の理想形に近い働きです。
来季への含意:先発回帰か、勝ちパ固定か——“二刀の役割価値”を手にした一年目
1年目から先発の地力と救援の即効性の両方を実戦で証明できた意義は大きいです。健康面のマネジメント最優先は大前提として、
-
先発回帰なら:直球のゾーン品質と初球ストライク率の底上げ、カウント球スライダー系の安定化が鍵。
-
救援継続なら:スプリットの見せ方を増やし(ボール先行→見せ球→勝負球の逆算)、クイックや牽制の微修正で走者対策を詰める。
現場(ロバーツ監督)は**「固定のクローザー」と断定せず**、対戦相性/ゲーム状況で柔軟に最終回を取りに行く運用を示唆。“勝つための最適解”に自分の役割を当てはめる姿勢が続く見込みです。
主要成績(2025)
-
レギュラーシーズン(MLB):10試合(先発8)36.1回 1勝1敗 ERA 4.46、28K、WHIP 1.43
※離脱前(先発時)は8先発34.1回 ERA 4.72。9月に復帰し救援へ。 -
ポストシーズン通算:9登板 10.2回 0.84、3セーブ(WC 1登板、NLDS 3登板〔セーブ2+3回完全〕、NLCS 3登板〔セーブ1、初戦1失点〕、WS 2登板無失点)
-
ワールドシリーズ内訳:2登板 2.2回 0失点(Game3:1.2回無失点、Game6:1.0回無失点、HBP1)
結論:評価は“期待株”から“勝利の方程式”へ
2025年の佐々木朗希は、「先発で苦しみ→負傷→役割転換→短期決戦で最適化」というドラマを一気に駆け抜けました。WSの極限でもゼロで帰るという救援の真価を体現し、チームの連覇に不可欠な歯車となったのは疑いようがありません。シーズンの入り口で抱かれていた「未知数」の評価は、秋の終わりには**「勝利の方程式の一角」へとアップグレード。来季は健康管理を前提に先発・救援どちらでも価値を最大化できる、極めてレアな“二刀の役割価値”**を携えてキャンプに入るはずです。
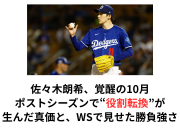
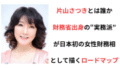
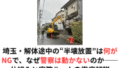
コメント