いま起きていること
2025年9月2日、自民党は参院選(7月20日投開票)の敗北を総括したのち、党四役の一角である小野寺五典・政調会長が辞任の意向を表明しました。小野寺氏は「政策の責任者の一人として、結果に責任を取るべきだ」と述べています。併せて森山裕幹事長、鈴木俊一総務会長らも辞意を伝え、党執行部は事実上の総退陣モードに入りました。
この流れを受け、石破茂首相(当時の党総裁)は9月7日に総裁辞任を正式表明。自民党は10月4日に臨時総裁選を実施し、高市早苗氏が新総裁に選出されました。
新体制づくりの一環として、高市総裁は10月6日、政調会長に小林鷹之・元経済安全保障担当相を起用する方針を固めています。
「政調会長」とは?——役割と権限の基礎知識
党三役の一つ
自民党の「党三役」は、幹事長・政調会長・総務会長を指します。幹事長が資金・人事・選挙・国会対策など党運営の中枢を担い、政調会長は政策立案を司る「政務調査会」のトップ、総務会長は党の最終意思決定機関である総務会の運営を統括します。
政調会長の具体的な仕事
-
政策立案の統括:各部会や調査会を束ね、政府提出法案・予算案・政権公約などを党内手続きに乗せて磨き上げます。
-
官邸・省庁との調整:党側の要望や修正を、官邸・各省と擦り合わせ、与党としての着地点をつくります。
-
党内コンセンサス形成:利害の異なる部会・族議員・地方組織の意向を調整し、総務会決定まで運びます。
こうした機能は、自民党が「政策政党」と呼ばれるゆえんであり、過去の政調会長経験者には後に総裁・首相に至る政治家も少なくありません(制度解説・沿革)。
なぜ辞職に至ったのか
参院選敗北の総括と「引責」
2025年7月の参院選で自民党は大きく議席を減らし、9月2日の両院議員総会で総括を実施。これを受け、小野寺政調会長は「政策責任者としての引責」を理由に辞任の意向を表明しました。同日に森山幹事長、鈴木総務会長も辞意を示し、執行部は一斉に身を引く流れとなりました。
党内政局の転回点:総裁交代へ
9月7日、石破首相は総裁辞任を表明。米国との通商交渉に一区切りがついたことや参院選敗北に伴う党内責任論が背景にあると説明しています。その後の総裁選(10月4日)で高市早苗氏が勝利し、党執行部・内閣の人事刷新が進みました。
後任人事の方向性
高市総裁は、政調会長に小林鷹之・元経済安全保障担当相を充てる方針を固めました。経済安保の知見を政策調整の中枢に据える狙いがうかがえます(10月6日時点の報)。
元政調会長・小野寺五典氏のプロフィール
-
氏名:小野寺 五典(おのでら・いつのり)
-
生年:1960年5月5日(宮城県気仙沼市出身)
-
学歴:東京水産大学(現・東京海洋大学)、東京大学大学院法学政治学研究科修了
-
経歴要点:宮城県職員、松下政経塾研究員、東北福祉大学助教授を経て、1997年に衆院議員初当選。外務大臣政務官、外務副大臣、防衛大臣(第2次安倍内閣:2012–14、再任:2017–18)、衆院予算委員長、自民党組織運動本部長などを歴任。2024年以降、政務調査会長。選挙区は宮城5区。
小野寺氏は外交・安全保障分野に強みを持ち、防衛相としての経験に裏付けられた政策運営を党政調にも持ち込みました。一方、2025年参院選の敗北を受け、党の政策面での責任を明確化するため身を引く判断を示した格好です。
「政調の仕事」の具体像——制度面から見る重要論点
-
部会主義:自民党は各政策分野ごとに部会を置き、現場感のある論点を吸い上げます。政調会長は部会間の縦割りを乗り越え、横断テーマ(物価・少子化・防災・地域経済など)を束ねます。
-
政府との「与党調整」:法案・予算編成の山場では、官邸・各省と深夜まで協議が続きます。ここでの着地点づくりが政調会長の腕の見せ所です(制度解説)。
-
総務会決定への橋渡し:政調でまとめた案を総務会で党決定に格上げします。最終決定機関と政策立案の接着点を担うのが政調会長です。
今回の辞職が意味するもの——3つの視点
「引責」の明確化とガバナンス
選挙結果に対する責任を、政策・運動・選挙の各機能別に明確化したことは、党ガバナンスの観点からは教科書的な対応です。政調会長の辞任は、政策コミットメントの総点検と党の再設計に向けたシグナルとも言えます。
総裁交代と「政策の再起動」
石破総裁の辞任 → 高市新総裁の誕生という大きな節目のなかで、政調会長交代は政策体系の「再起動」を象徴します。新体制では、経済安保や経済対策を核に、物価・賃上げ・産業競争力・社会保障・地方創生の横串設計が求められます。小林鷹之氏の登用方針は、その方向性を端的に示しています。
与党内「政策政党」機能の再定義
自民党の強みは「政調—総務会—官邸」を通じた政策形成の回路にあります。今回の引責と人事刷新は、部会主義の強化や官邸主導とのバランス、地方の声の再吸収といった永年課題への再挑戦でもあります。
タイムライン
-
2025年7月20日:参院選で自民党が議席を減らす。
-
9月2日:党総括ののち、森山幹事長・小野寺政調会長・鈴木総務会長らが一斉に辞意表明。
-
9月7日:石破首相が総裁辞任を正式表明。
-
10月4日:自民党総裁選で高市早苗氏が勝利。
-
10月6日:政調会長に小林鷹之氏を起用する方針(報道)。
主要登場人物のミニ事典
-
小野寺五典(元政調会長):防衛相を2度務めた安保通。党政調会長として政策調整を統括。参院選敗北の総括を受け辞意。
-
高市早苗(新総裁):2025年10月4日に総裁選勝利。初の女性首相就任が見込まれる。
-
小林鷹之(次期政調会長方針):経済安全保障担当相(2021–22)を歴任。政策立案の中枢で経済安保の視点を生かす見通し。
-
石破茂(前総裁・前首相):9月7日に辞任表明。通商交渉の区切りと選挙結果を背景に判断。
今後のチェックポイント
-
政調体制の編成:部会・調査会の人事と優先アジェンダ(物価・賃上げ・防衛・エネルギー・地域経済)。
-
官邸との役割分担:政策決定プロセスの透明性・スピード感の両立(政調→総務会→閣議・提出のリズム)。
-
総務会の運営:党内コンセンサスの形成力回復。地方組織・連立与党との調整窓口としての機能。
まとめ
政調会長は、自民党の政策形成システムの要に位置する重職です。今回の辞職は、選挙結果を踏まえた責任の明確化とともに、政策政党としての再設計を進める「起点」でもあります。総裁交代と政調会長交代が同時並行で進むことで、与党内の政策回路は大きく組み替わります。新政調のもとで、部会主義の強みを再興しつつ、官邸・省庁との一体運営をどこまで高い精度で実現できるかが、これからの成否を左右します。

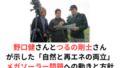
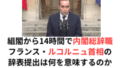
コメント