国の紹介
-
タンザニア:東アフリカの旧タンガニーカ+ザンジバルから成る連合国家。公用語はスワヒリ語・英語。宗教はキリスト教とイスラムが大宗で、ザンジバルはイスラム色が極めて濃いのが特徴です。
-
ナイジェリア:アフリカ最大級の人口・経済規模。公用語は英語、宗教は北部イスラム、南部キリスト教の二大勢力が拮抗し、宗派間の摩擦が政治・治安に影響しがちです。
-
ガーナ:英語圏の西アフリカ民主国家。宗教はキリスト教が多数派、イスラムや伝統宗教も一定の比率を保ちます。
-
モザンビーク:ポルトガル語圏の南部アフリカ国家。宗教はキリスト教が多数、イスラムも少なくありません。北部では過激派による不安定化が続いた地域もあります。
4か国の渡航危険度
危険度クラスの意味(外務省)
-
レベル1:十分注意してください
-
レベル2:不要不急の渡航は止めてください
-
レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)
-
レベル4:退避してください。渡航はやめてください(退避勧告)
| 国 | 全体の基調 | 高リスク地域(例) | メモ |
|---|---|---|---|
| タンザニア | 多くはレベル1 | レベル3=キゴマ州西部(ブルンジ国境付近)/ レベル2=ムトワラ州 | 沿岸部(ザンジバル含む)やアルーシャ州はレベル1(十分注意)。武装強盗・越境リスクの注意喚起あり。 |
| ナイジェリア | 全国がレベル2以上 | レベル4=北東3州(ボルノ/ヨベ/アダマワ)/ レベル3=北西・北中部など広域 | テロ・誘拐・暴動リスクで広範囲がレベル3以上。首都圏(アブジャ)はレベル2。 |
| ガーナ | 多くはレベル1 | レベル2=ブルキナファソ国境地帯やトーゴ・コートジボワールの一部国境地帯、アッパー・イースト州の一部 | 近隣国情勢の影響で北方や一部国境地帯が引き上げ。 |
| モザンビーク | 南部~中部の多くがレベル1 | レベル3=カーボ・デルガード州(ペンバ市除く)+ナンプラ州の一部/ レベル2=ペンバ市、ニアッサ州メクーラ郡 | 2025/7/4に一部引き下げ(首都圏などレベル1)。北部の反政府勢力関連リスクは継続。 |
経済力(所得階層と1人当たり所得の目安)
世界銀行の所得区分では、タンザニア・ガーナ・ナイジェリアは「下位中所得国」、モザンビークは「低所得国」に入ります。区分は毎年7月に更新され、Atlas法GNIで判定されます。
購買力平価(PPP)ベースの1人当たりGDPの最近値(概数)は以下の通りで、生活実感の差を概ね反映します(国際$=米国の購買力で調整したドル):
-
ガーナ:約 8,027(2024)
-
ナイジェリア:約 6,207(2023)
-
タンザニア:約 4,221(2024)
-
モザンビーク:約 1,678(2023)
日本と比べると、全体として一人当たり所得は大幅に低い水準です。
低賃金ゆえに日本の労働市場から見れば「安価な労働力」として捉えられがちですが、後述の通り、コストは賃金以外の箇所(教育・生活支援・管理・離職/失踪リスク)で膨らみます。
宗教(受入れ側の配慮コストを伴う前提)
-
タンザニア:キリスト教とイスラムが2大宗教(ザンジバルはイスラム優位)。
-
ナイジェリア:イスラム(主に北部)とキリスト教(主に南部)が拮抗。宗派差が文化実務に直結します(休日、食、装い等)。
-
ガーナ:キリスト教多数、イスラム少数、伝統宗教も一定。
-
モザンビーク:キリスト教多数、イスラムも有力。
日本側の運用上の現実問題として、ムスリム対応(礼拝時間・礼拝場所・ラマダン時の就労配慮・ハラール食)や、土葬文化への対応が不可避です。
日本は火葬率が99%超で、土葬できる墓所はごく限られます。
土葬(=遺体を土中に葬ること)は、許可を受けた「墓地」以外では不可。
自宅の庭や山林に埋めるのは違法です。
自治体・墓地の運用上、ムスリム用の土葬区画の不足が現に指摘されています。
犯罪率(性犯罪も):数字の「見た目」にご用心
まず大前提として、「警察に記録された性犯罪」や「レイプ率」の国際比較は不適切になりやすいです。
犯罪の定義・通報慣行・統計の取り方が国ごとに大きく異なり、UNODC(国連薬物犯罪事務所)自身が“比較は慎重に”と明言しています。
つまり「数字が低い=安全」ではありません。
比較的定義が揃いやすい殺人(故意の殺人)で見ても、日本は世界最低水準(最新年で0.23/10万人)に対し、
-
ガーナは 約2/10万人(2021)、タンザニアは 約4/10万人(2020)、ナイジェリアは 約22/10万人(2019)と、概ね日本より高いのが実情です。
-
モザンビークは年次・推計に揺れがありますが低い一桁台の推計が多い—ただし統計精度に留意が要る、というのが妥当な見方です。
性暴力(親密なパートナーによる過去12か月の暴力=SDG 5.2.1)は、公式統計の更新に時間差があり、国別・年次でばらつくのが現実です。
WHO/UN Womenは12か月有病率の国際指標を提示していますが、一律比較は不可、という立場です。
たとえばタンザニアでは近年の調査で過去12か月のIPV(身体22%・性的16%)規模が報告される一方(調査法に注意)、いずれの国も日本の公的統計より高い水準が一般的です。
加えて、公衆衛生の観点ではHIV有病率が採用・配置・健康管理の設計コストに直結します。
UNAIDSの成人有病率(15–49歳)は、モザンビーク約11%台、タンザニア約4%前後、ガーナ約1–2%、ナイジェリア1%強が最新推計の目安です。
日本は桁違いに低い水準です。
技能実習生・育成就労などで来日した場合に「現実に起きうる懸念」
人数が少ないから問題ではないという論法は危うく、制度側が備えるべき“隠れコスト”と“失敗リスク”を直視すべきです。
教育・管理コストの過小見積り
-
言語:英語圏(ガーナ・ナイジェリア)とスワヒリ語圏(タンザニア)、ポルトガル語圏(モザンビーク)が混在。
現場日本語教育・通訳配置・安全教育の固定費が膨らむ割に、離職・転籍・帰国で投資回収できないリスクが常に残ります。 -
宗教・習俗:礼拝時間、ハラール対応、土葬ニーズ等は勤務地・寮の運用に直撃。
火葬一辺倒の日本で、死後の配慮の制度設計は未整備が目立ち、企業単体では解決不能です。
労働・生活のミスマッチ
-
物価差・賃金差を目当てに来日しても、手取りが想定を下回ると不満・離職に直結。
受け入れ側の残業管理・住環境・送金支援が不十分だと、非正規就労や失踪の温床になります(制度名が変わっても、運用の質が上がらなければ再発)。 -
医療アクセス:HIV等の慢性疾患フォロー、産業保健(ワクチン、結核・肝炎スクリーニング等)を会社側が現実的に担えるのか。
ここを怠ると職場内感染リスクや長期欠勤の形で跳ね返ります。
受入れ地域社会の摩擦
-
生活ルールの共有不足(ごみ出し、騒音、礼拝場所、断食時の勤務配慮など)から近隣トラブルが発火。
-
交通・住宅・教育(子どもがいる場合)・多言語行政窓口など、自治体側の恒常コストが増大。企業は雇用主として地域調整の“後始末”まで見越した費用と人員を確保すべきです。
-
治安不安のレッテル貼りは誤りですが、通報慣行の違いや女性保護の回路(相談先・避難)が脆弱だと、見えない被害が積み上がります。
UNODCが指摘するように統計は氷山の一角で、教育・監督体制の未整備こそが最大のリスクです。
企業にとって本当に“得”なのか
-
「安価な労働力」という幻想は、離職・転籍・失踪・再募集・再教育の総コストを計上すると容易に吹き飛びます。
-
制度が「技能移転」を掲げても、実務は単純作業中心になりやすく、育成投資の回収も曖昧。監理団体任せの受入れでは、現場にノウハウが蓄積しない=生産性は上がらないという本質的欠陥が残ります。
日本との違い
-
人口構成:日本は世界最高齢水準(中央値約49.5歳)。一方、アフリカ諸国は若年人口が厚い。若者の流入は潜在的にはプラスですが、教育・言語・資格のギャップを埋める投資が前提です。
-
法・統計の互換性:犯罪・労働・保険医療の制度・定義が非互換で、数字の単純比較は誤解を招く(特に性犯罪)。
制度設計は“最悪ケースに耐える”前提で作るべきです。 -
文化・宗教運用:礼拝・食・弔い(火葬原則の日本 vs 土葬を原則とするイスラム)といった生活の根っこにまで踏み込む整備が必要。
今の日本は土葬受け皿が極小で、行政・墓地運用を含めた制度的遅れがはっきりしています。
ここまでを踏まえたまとめ
「まず人数ありき」の受入れ拡大は危うい。
受入れ国側が支払うべき見えない固定費(言語・宗教・医療・住宅・地域調整・統計の非互換への対策)を制度と予算に明記し、企業に丸投げしないこと。
さらに、犯罪・性暴力の“国際数字”を政策根拠にするのは禁物です。
UNODCが繰り返す通り、定義・通報・記録の差で数字は大きく揺れます。
治安不安を煽るよりも、現場の教育と監督、女性保護の回路、医療アクセス、宗教実務の運用など、実務の土台を作るほうが効果的です。
企業視点でも、短期の人件費メリットより、離職・再教育・地域摩擦のコストが重いのが現実です。
受入れを続けるなら、人材育成を“投資案件”としてフルコストで設計し、言語・宗教・医療・生活支援を組み込んだ職場インフラを先に用意する。
これができないなら、受入れ規模の拡大は制度疲労と社会的反発を招く「負け戦」になります。
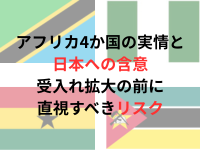


コメント