2025年10月4日、自民党総裁選は高市早苗氏が決選投票で小泉進次郎氏を退け、新総裁に選出されました。得票は高市氏185票、小泉氏156票。日本初の女性首相誕生の可能性が現実味を帯びる一方で、小泉氏は“あと一歩”に届かなかった理由を直視せざるを得ません。本稿では、①今回の総裁選の結果、②小泉氏のこれまでの実績の「薄さ」、③選挙戦で噴出したステマ問題・神奈川の党員離党処理疑惑、④それらが「実力不足」という評価にどうつながったのかを検証し、最後に再起への最低条件をフォローとして提案します。なお、数値や事実関係は公開情報に基づいています。
総裁選の結果が示したもの
決選投票の最終結果は高市185—小泉156。情勢報道では「世論人気は小泉」という空気が序盤にありましたが、票読みの現実は異なりました。国会議員・党員算定票の双方で上積みできなかった小泉氏に対し、高市氏は地に足のついた組織戦と政策メッセージの“筋”で議員心理をとらえた格好です。結果の数字そのものが、最終盤での説得力の差と、危機管理の巧拙を雄弁に物語っていると受け止めます。
「実績がない」の中身――肩書はあるが、成果が見えない
環境相時代:話題先行、実務は霞んだ
2019年の国連関連イベントで「気候変動の取り組みは楽しく、クールで、セクシーであるべき」と語った発言は強烈な拡散力を持ちました。しかし、発信の華やかさに比べて制度・予算・KPIで語る“実”がどこまであったかは検証が必要です。レジ袋有料化は経産省・環境省が進めた全国一律措置として一定の行動変容を生みましたが(辞退率の上昇や出荷量減少などの統計)、プラごみ全体に対する寄与や代替袋増加の副作用をめぐる論争も続き、政策リーダーとしての成果物を自らの統治能力に帰属させることには成功しませんでした。発信はできても、実務の総合ディレクション力が見えづらかったのです。
農林水産相として:任期は短く、“統治”の見せ場を作れず
2025年5月の農水相就任はチャンスでした。米価、食料安保、スマート農業など生活直結のテーマは「実力」を見せるには格好の舞台でしたが、総裁選日程と重なり政策実装の成果を可視化する時間は短く、目に見える制度設計や合意形成の“山”を作るところまで至っていません。任に就いたこと自体は事実でも、「何を決め、何を動かしたのか」という検証可能な実績は薄いまま選挙戦に突入しました。
要するに、「肩書や露出は多いが、成果の輪郭が曖昧」という評価が、党内外に蓄積していたと考えます。
敗因①:ステマ(やらせコメント)疑惑が信頼を削った
選挙期間中、小泉陣営が動画配信プラットフォーム(ニコニコ)で“小泉氏を称賛するコメント”の投稿を陣営内に要請するメールを出していた、とする報道が出ました。記事は例文リスト(24パターン)や他候補への中傷に類する文言の存在を具体的に示し、続報では陣営側の関係議員が「事実関係を大筋で認めた」との言及もありました。広報班長を務めていた牧島かれん元デジタル相は職を辞任し、疑惑は鎮火し切らないまま投票日を迎えています。
もちろん、小泉氏側は一部報道を「事実に反する」と反発もしています。しかし、危機対応のセオリーから見れば、「要請メール」という“形のある証拠”が公に流通した時点で、否定一辺倒では支持回復が難しく、早期の説明・再発防止策・責任区分の明確化が必要でした。結局、選挙終盤の数日間が“説明と火消し”に割かれ、政策論争の露出が相対的に減ったことは否めません。
影響の実相
・中間層の“公正さ”感度:小泉氏のコア支持層よりも、まだ支持を決めかねていた中間層・無派閥寄りの議員や党員にとって、組織的な演出は抵抗感が強いテーマです。
・デジタル戦術の逆回転:SNS/動画空間で強かったはずの陣営に「やらせ」の烙印が押されると、強みがそのまま弱みに転じます。
・最後の伸びの阻害:決選投票では、1回目に他候補へ流れた票をどれだけ吸引できるかが勝敗を分けます。スキャンダルはその合流を鈍らせました。実際、決選投票で高市氏は議員票・党員票ともに上積みし、小泉氏を突き放しました。
敗因②:神奈川での“党員離党処理”疑惑が地元の足場を揺らした
投票直前、「小泉氏の地元・神奈川県で、高市氏支持の党員826人が本人の意思確認なく離党扱いにされていた」という週刊誌報道が出て、党員投票の公正性をめぐる論争が噴出しました。関連して、党本部の総裁選挙管理委員会が党員数の訂正を発表していたことも取り沙汰され、疑惑の陰影は濃く映りました。
これに対し、神奈川県連は「誤った印象を与える」と抗議し、小泉氏側も報道への反論を表明しています。真相は党調査と検証に委ねられるべきですが、“地元で不自然な名簿操作”という疑惑それ自体が、地元発のモメンタムを冷やす効果を持ったことは否定できません。とくに「総裁選の公正さ」に繊細な党員・地方議員ネットワークの空気が重くなり、最終盤の引き締めにブレーキがかかったとみられます。
敗因③:危機管理とメッセージの“芯”が最後にぶれた
政治家小泉進次郎の最大の資産は、分かりやすい言葉で大局を語る発信力です。2019年の国際舞台でのメッセージが象徴するように、若い世代を引きつける言語感覚は稀有です。一方で、“言葉が走りすぎて、実務が追い付かない”という評価も併走してきました。
今次の総裁選では、本来は政権運営の「中核政策(生活と安全保障、経済・エネルギー、農水分野)」で最後のひと押しを仕掛ける局面でした。しかし、ステマ疑惑・神奈川名簿疑惑という二重の火消しに追われ、「小泉ならではの政策の芯」が最終週に埋没した印象があります。本人は敗戦の弁で“力不足”に収めましたが、選択肢としては、①早期の第三者調査の受け入れ表明、②広報責任の明確化、③地元での党員向けタウンホール開催――など、“説明責任を自ら取りにいく”積極対応がもう一段必要でした。
総括:実績の乏しさ+危機管理の稚拙=「実力不足」という評価
以上を踏まえると、小泉氏の敗因は「実績がない」ことに尽きる、というより**“実績が見える形で積み上がっていない”**ことにあります。
-
政策実行の棚卸し不足:環境相・農水相として、制度・予算・KPIで検証できる“自分の決定”を提示できなかった。
-
危機管理の遅れ:ステマ問題での初動対応・説明責任・再発防止の提示が遅く、信頼を削った。
-
組織基盤の緩み:神奈川の党員数訂正をめぐる疑念が地元の求心力を低下させた。
これらが相まって「人気はあるが、政権を任せられる執行者か」という問いに“NO寄り”の票が積み上がった――それが185対156という数字の背景だと考えます。
それでも残る「フォロー」――再起への最低条件
厳しく指摘してきましたが、ここからは建設的なフォローです。小泉氏は依然として、①国民的な知名度、②若年層への到達力、③メディアの注目を集める発信力、という希少資産を持っています。これを実力に変える道筋は明確です。
実績の“見える化”を最優先に
-
1案件でいいから、骨太にやり切る:例えば農政なら、備蓄米の機動運用や生産性向上のKPI(収量・付加価値・就農年齢など)を定め、予算措置と制度運用の順番まで設計して公開します。四半期ごとに進捗を“見える化”するだけで評価は一変します。
デジタル選挙のガバナンスを制度化
-
広報ルールの明文化と第三者監査:称賛投稿の要請メールのような“グレー”を二度と生まないガイドラインを、公表・監査・教育までセットで仕組みにします。危機後のガバナンス強化をやり切れば、逆に「学習する政治家」としての評価が得られます。
地元台帳の透明化で「疑念ゼロ」へ
-
神奈川モデル:党員台帳の更新履歴、資格確認フロー、第三者点検を公開し、他県へ横展開します。疑念の土壌を断ち切るのは透明性しかありません。
結語
今回の総裁選は、肩書や人気では執行の正統性は得られないことを再確認させました。小泉進次郎氏の敗因を一言でいえば、「実績の見える積み上げが乏しく、危機管理でも後手に回った結果、“実力不足”という評価が固まった」ことにあります。
ただし、政治における評価は可逆です。一つの案件をKPI付きでやり切り、デジタル広報と地元組織の透明性を“仕組み”で担保する――この三つを半年で実行できれば、次のチャンスは必ず巡ってきます。発信の力は、正しく設計された実行力に接続したとき初めて武器になります。そこに踏み込めるかどうかが、次の総裁選での真価を決めると考えます。
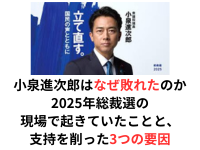

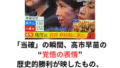
コメント