新制度「育成就労」とは?
育成就労は、2024年6月に成立・公布された改正法で新設される在留資格です。
人手不足の分野でおおむね3年間の就労を通じて人材を育成し、終了後は「特定技能」へ橋渡しすることを狙います。
施行は公布(2024年6月21日)から3年以内に政令で定める日で、遅くとも2027年6月21日までに始まります。
制度の運用では、分野ごとに“受入れ見込数”を上限として管理する方針が示されています。
なぜできたのか
従来の技能実習は名目上「国際貢献(技能移転)」でしたが、実態は国内の人材確保の色彩が強まり、転籍の硬直性・高額あっせん料・権利侵害や失踪などの問題が重なっていました。
政府の有識者会議は2023年11月の最終報告で、目的を「人材育成+人材確保」へ明確化し、監督・保護を強化して特定技能と一体で回す再設計を提言。
これを踏まえて法整備が進んだ経緯です。
技能実習生とは?
日本で一定期間、現場のOJT(就業訓練)を通じて技能・技術・知識を学び、開発途上国等に移転することを目的とした制度です。
1993年に制度創設、2017年には専用法(技能実習法)が施行され、目的や保護規定・監督体制が明文化されました。
実習は企業が雇用し、労働関係法令が適用されます。
受け入れの枠組み
-
実習実施者(受け入れ企業):雇用主としてOJTを提供
-
監理団体:商工会など非営利が多く、計画の管理・指導を担う(「団体監理型」)
-
OTIT(外国人技能実習機構):監督・相談窓口・指導勧告などの中核機関
-
送り出し機関:相手国側の公的/準公的機関や認定機関
どのくらいの規模?
-
在留する技能実習生:2024年末で456,595人(前年比+52,039)。全国の実習生の98.4%が団体監理型で、企業単独型は1.6%です。
-
主な国籍はベトナム(46.5%)・インドネシア(22%)・フィリピン(8.9%)・ミャンマー(7.9%)など。
制度の段階(1号→2号→3号)
| 区分 | 目的・位置づけ | 在留のめやす | 主な進級要件 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 入国~1年目の修得 | 最長1年 | 基礎級・初級相当の試験合格 等 |
| 2号 | 2~3年目の習熟 | 最長2年(累計3年) | 3級(実技)等の合格、受け入れ先・監理団体が「優良」 等 |
| 3号 | 4~5年目の熟達 | 最長2年(累計5年) | 2号要件の達成を前提に職種要件などを満たす |
主な業種・配置
建設、食品製造、機械・金属などの人手不足分野で受け入れが多いのが実態です
ここが変わります(技能実習 → 育成就労)
| 観点 | 旧:技能実習 | 新:育成就労 |
|---|---|---|
| 制度目的 | 技能移転(国際貢献) | 人材育成+人材確保(特定技能へ接続) |
| 期間 | 最長5年(1・2・3号の累計) | 原則3年(再受験等で最大+1年の延長規定) |
| 転籍(職場変更) | 原則不可(例外のみ) | 一定要件を満たせば本人意向でも可(同一業務区分・就労期間・試験合格等) |
| 日本語・技能 | 明確な段階要件が弱い | 日本語A1→A2等の段階設定+技能試験で確認 |
| 枠管理 | 実質横断的 | 分野ごとの受入れ見込数=上限で運用 |
| 監理主体 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制)、外部監査の義務化 |
| 行政体制 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人育成就労機構に再編(認定・相談・監督を強化) |
| 送出し・費用 | 高額手数料などが課題 | 政府間取決め(MOC)国に限定/費用の透明化 |
いま何が問題で、失踪はどれくらいか
技能実習では、転籍が難しいことや借金型のあっせん、労務違反・人権侵害の訴えなどが構造的な火種になってきました。
失踪は政策判断上も重い課題です。
-
2023年(令和5年)の失踪者:9,753人(比率1.9%)で過去最多。
-
2024年(令和6年)は6,510人(1.2%)と前年から3,243人減(▲33.3%)の暫定集計が公表されています。
改定で本当に改善するのか
期待できる点として、
-
転籍の明確化・拡充により、逃げずに労働環境を改善する道ができます。
-
監理支援機関の許可制と外部監査、新機構による一体監督で、運用の実効性が高まる設計です。
-
分野別上限で量を管理し、日本語・技能の段階要件で“育てて残す”筋道が明文化されました。
一方で、実効性は省令・運用次第です。
とくに①転籍要件(分野ごとに1~2年等)の運用、②監査の厳格さ、③送出し費用の実地監督が緩むと、旧来の問題が残り得ます。
ここは公表KPI(失踪率・未払い率・監査件数等)での継続監視が欠かせません。
失踪者への対応(罰則・強制送還は可能か)
-
「失踪」そのものに独立の犯罪名はありませんが、本来の活動を一定期間行わない等に当たれば在留資格の取消し対象になり得ます。その後、不法残留(オーバーステイ)や無資格就労に至れば入管法70条等の罰則(3年以下の懲役・禁錮または300万円以下の罰金等)の適用対象です。
-
条件を満たせば退去強制(強制送還)が可能で、退去強制された者の上陸拒否期間は原則5年です。出国命令制度を使って自発的に出国した場合は上陸拒否期間1年となります(いずれも例外規定あり)。
-
2024年の改正では、長期収容に代わる「監理措置」が導入され、社会内での管理下で手続を進める仕組みも整えられました。
まとめ
育成就労は「看板の掛け替え」で終わる懸念が強いです。
制度目的を“育成+確保”に言い換えても、失踪の土壌(転籍の壁/高額あっせん費用/監督の弱さ/データ非公開)が残れば、実態はほとんど変わりません。
こうでなければまた同じです
-
転籍は“被害発生時は即時”を明文化(年数要件なし、証拠初期評価で保護→後追い審査)。
-
送出費用の“実質ゼロ化”+違反は受入停止・名公表・刑事告発までセットで。
-
四半期KPIの全面公開(失踪率・所在把握内訳・未払い率・監査件数・転籍成立率・監理機関の処分状況)。
-
無通告監査と即時停止の発動基準をガイドラインで数値化(未払い1件=新規受入停止等)。
-
自治体・現場への財源措置(学校のJSL人件費、医療通訳、相談員を国費で恒常化)。
本当に変えるのは名称ではなく、数字(KPI)と罰則の重さ、公開の度合いです。
ここを曖昧にしたまま拡大すれば、失踪・搾取・地域負担の再演になります。
制度の評価はどれだけ公開し、どれだけ止め、どれだけ救済したかで測るべきでしょう。


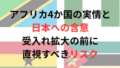
コメント