10月8日、立憲民主党の本庄知史政調会長が記者会見で、各党が検討を進めるスパイ防止法の制定に懸念を示し、「まだ協議の段階ではない」といった趣旨を述べました。報じられた内容を読む限り、主眼は「外国勢力と通じた“日本人”も摘発対象になり得る以上、人権侵害のリスクがある」という指摘です。要するに“立法の前に、さらに慎重に議論を”という姿勢です。ですが、この物言いは、実務面・国益面・政治姿勢のすべてにおいて失点が大きいと言わざるを得ません。まずは事実関係を押さえたうえで、何が問題なのかを順に指摘します。
「慎重に議論」――聞こえは良いが、実務を止める常套句です
立法府で「慎重な議論」を求めるのは結構ですが、安全保障に関する“立法設計の宿題”を先送りし続けた40年が、今日の脆弱さを温存してきたのも事実です。1985年に自民党が提出した通称「スパイ防止法案」は審議未了で廃案となり、その後も包括的なスパイ行為処罰法は実現していません。当時は日本弁護士連合会などが「人権侵害の危険」を理由に反対し、結果として国会は結論を出さないまま時を費やしました。“慎重論”は40年前からほぼ同じ言葉で繰り返され、立法の空白だけが残ったのです。
2013年の特定秘密保護法は“漏えい後”の罰則軸であり、スパイ行為そのものを横断的に網羅する仕組みではありません。国際機関や人権団体が過去に表明した懸念も踏まえ、「濫用されない仕組み」を初めから法文に織り込めばよいのであって、立法自体を停止する口実にはなりえません。
現実は待ってくれません――国内外の“実害”は積み上がっています
「実態が定かでない」という趣旨の発言は、現場の肌感覚からかけ離れています。たとえば――
-
ソフトバンク元社員による機密流出事件(2019年の不正取得、2020年逮捕)。在日ロシア通商代表部関係者に営業秘密を渡したとされ、有罪が確定しています。対外工作と国内企業の内部犯の接点を示した典型例です。
-
産総研職員の逮捕など、国家の重要技術が「ヒト」を経路として流出する事案が継続的に発生。政府の有識者会議資料でも「漏洩が後を絶たない」と明記されています。
-
中国での邦人拘束は2015年以降少なくとも17人。相手国は反スパイ法を強化し適用範囲も拡大しています。国際環境が厳しくなるほど、自国の情報保護体制が問われるのは当然です。
-
東芝グループ子会社の図面データが中国側へ流出か――2025年10月には不正競争防止法違反容疑で逮捕者も出ました。産業技術の流出は“いまこの瞬間”の国内問題です。
このように、被害例は事件記録と公的資料でいくらでも枚挙できます。それでもなお、「実態が不明」として“協議すら遠ざける”のは、政治として職責放棄ではないでしょうか。
「人権が大事」なら、なおさら法案テーブルに着くべきです
本庄氏は人権侵害のリスクを語ります。ならば**“拒否”ではなく“設計”にコミットすべきです。具体的には、以下のセーフガード条項**が議論の出発点になります。
-
罪名・構成要件の厳格化:対象となる「国家秘密」「保護すべき技術・情報」を限定列挙し、過度に広く取らない。
-
令状主義の徹底・二重の司法審査:捜索・傍受・凍結等には司法審査を二段構えで義務づけ、緊急適用にも事後審査を必須化。
-
公益通報・取材保護の明文規定:公益目的の取材・報道は処罰対象外であることを条文に書き込み、適用除外の範囲と立証責任を明確化。
-
独立監督機関の設置:行政から独立した第三者監督で秘密指定・捜査の妥当性を** ex ante / ex post**でチェック。
-
日弁連や報道界・学界の常設協議:運用指針を公開プロセスで定期更新し、年次報告を義務づける。
過去の特定秘密保護法をめぐる懸念は真摯に受け止めるべきです。しかし、立法に反対するための懸念」から「立法を適正化するための懸念」へ――ここに発想転換が要ります。立法府の役目は危険を言い当てて手を止めることではなく、その危険を“制度で潰す”ことです。
「協議の段階ではない」――それ、国会で一番言ってはいけない言葉です
報道ベースでは、本庄氏は「まだ法案に賛否で協議する段階ではない」との姿勢でした。ここが最大の問題点です。与野党が「定義」「取材保護」「監督」「濫用防止」の4点で対案を叩き合うべきタイミングに、「協議から降りる」ことは野党第一党の自殺点です。しかも同じ会見では、自民党の新体制を「人事ができないリーダー」と手厳しく評しておきながら、自党は安全保障の根幹法制のテーブルに出ない――ダブルスタンダードに見えます。
政治は言葉の競い合いではありません。条文と監督設計こそが命です。立憲民主党が人権を大切にする政党だと自認するなら、なおさら人権セーフガード条文を自ら書き込ませる“交渉”にこそ進むべきでした。
「外国勢力と通じた“日本人”も対象になりうる」発言
**「外国勢力と通じた“日本人”も対象になりうる」→「人権侵害が起きかねない」→「だから今は協議に入らない」**というロジックは、結果として“現在進行形のスパイ被害”より“仮説的なリスク”を優先している印象を与えます。この“優先順位の誤り”が「擁護に聞こえる」批判を招いた本質であり、政治的判断としてはやはり拙劣です。
高市総裁への“言葉遊び”は、論点を軽く見せるだけです
本庄氏は同じ会見で、自民の役員人事を「麻生家に嫁入りした高市さん」と表現し、女性蔑視だと強い批判を浴びました。のちに“古い言葉を使ってしまった”と釈明しましたが、火に油を注いだ格好です。安全保障という重い論題のさなかに、ジェンダー感覚を疑われる表現で炎上を招いた政治判断は、率直にいって稚拙です。論点を人事の“言葉遊び”に逸らし、政策論争の地力を自ら削ってしまったのです。
立憲民主党が取るべき“建設的な対抗戦略”
痛烈に申し上げます。「慎重論」で存在感は出せません。野党第一党が“止める力”しか持たないなら、国民はやがて“代わりの推進役”に期待を移します。立憲がリベラル・人権派を標榜するなら、むしろ以下の**“攻めの人権設計”**で主導権を取り返すべきです。
-
対案の即時提示:①保護対象情報の限定列挙、②公益通報・取材の明文免責、③二重司法審査、④独立監督機関、⑤年次運用白書(統計・濫用事例ゼロ報告義務)――この5本柱を“骨”にした条文化を提示する。
-
比較法の可視化:英国のOfficial Secrets Acts、ドイツの対外貿易法・刑法セクション、米国のEspionage ActやFARAの濫用防止条項の比較表を作り、**“人権担保を組み込んだスパイ対策”**の国際標準を示す。
-
経済安保と一体設計:ヒト・モノ・カネに分けて、外為法・不競法・刑法改正との整合フレームを提示する(政府資料が認める“ヒト経由の流出”の現状から着手)。
-
検証と修正の“日没条項”:新法施行後5年で自動再検証。濫用が認められた条項は自動失効も含め再設計する“サンセット+レビュー”を入れる。
**“止める野党”から“設計する野党”へ。**これが、立憲民主党が政策政党として復権する唯一の道です。
結論――「危険だから作れない」のではなく、「危険だからこそ“作り込み”が要る」のです
-
事件・逮捕・国際環境の変化という現実の圧力は、既に目の前にあります。「実態が不明」だから議論を止める――その余裕はありません。
-
人権を守る最善手は、立法を拒むことではなく、立法の文言と監督を“人権仕様”にすることです。**条文で縛り、手続で縛り、監督で縛る。**これが近代立法の作法です。
-
「今いるスパイを擁護した」かのような露骨な言い回しは一次報道で未確認です。しかし、“協議拒否”という政治判断が擁護に見えるのは、立憲側の優先順位付けが誤っているからにほかなりません。
-
高市総裁への“嫁入り”発言のような不用意なレトリックは、政策論争の足場を自ら壊すだけです。安全保障×人権という難題に対し、言葉ではなく条文で勝負すべき局面です。
最後にもう一度強調します。「危険だから法を作れない」ではなく、「危険だからこそ、濫用不可能な法を作る」のです。立憲民主党が本当に“人権の党”を名乗るなら、スパイ防止法の協議テーブルの真ん中に座り、最も厳しい人権セーフガードを法文に刻み込む仕事を、ただちに始めるべきです。いま求められているのは、議論停止の美辞麗句ではなく、国と自由を同時に守るための制度設計です。
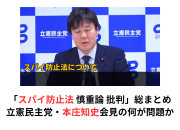
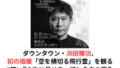
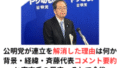
コメント