東京都議会・千代田区選出のさとうさおりさんは、公認会計士・税理士の専門性を武器に、予算や税制の“数字”から都政を問い直していく新世代のローカルリーダーです。2025年の都議選で初当選、現在は**無所属会派「やちよの会」**を率い、経済・港湾委員会に所属して活動していらっしゃいます。
本稿では、経歴・プロフィール、掲げる公約と政策の骨格、そして小池百合子知事(東京都)に対して厳しく指摘している論点を、できるだけ丁寧にご紹介します。政治的立場を超えて、都民の家計と地域の持続可能性に光を当てようとする姿勢を、好意的に評価する立場からまとめます。
プロフィールと経歴
-
生年月日:1989年7月28日(36歳)
-
出身・拠点:茨城県出身、現在は東京在住
-
資格:公認会計士・税理士
-
肩書:東京都議会議員(千代田区)、政治団体「減税党」党首
-
会派:無所属(やちよの会)/経済・港湾委員会所属
-
当選:2025年6月22日投開票の都議選・千代田区選挙区で7,232票を獲得し初当選。
会計事務所勤務を経て独立し、企業の内部監査や税務の現場で経験を重ねてこられました。会社経営にも関わり、障がい者や高齢者の積極雇用に取り組むなど、雇用政策の“現場”にも強みがあります。政治家を志した背景には、「共働きや介護・子育てが重なる現役世代の厳しさ」「制度が伴わない“形だけの女性の社会進出”」「止まらない増税」への問題意識があり、家計の可処分所得を増やす政治を一貫して打ち出してきました。
SNSや動画での発信力も顕著で、XやYouTubeを通じた政策解説や議会報告は大きな支持を集めています(自身の公式サイトでもフォロワー・登録者規模を公表)。
公約と政策の骨格(要旨)
減税・社会保険料の負担軽減・歳出改革
看板は**「減税」「社会保険料の負担軽減」「歳出改革」の三本柱です。とくに千代田区をモデルに「減税特区」を構想し、“貯め込みすぎの公金”は住民に返すべき**という会計士ならではの視点で「税の取り過ぎ」を是正すべきだと訴えます。
-
減税特区の提案:余剰金の多い自治体ほど、まず減税で住民に還元を。
-
インボイス制度の廃止を求める意見書:零細事業者の負担を直撃する制度は区・都から国に見直しを強く働きかける。
-
歳出改革の徹底:不要・不急・過大な施設整備より**“中身の支援”へ重点配分**。
現役世代と子育てへの集中投資
-
学童クラブの時間延長・対象拡大、保育の延長・“学童で習い事”など“時間の困りごと”に刺さる支援。
-
シッター利用など当面の“手当て”の拡充で、共働き世帯の安全・安心を確保。
-
豪華施設より支援の中身へ——高額の施設賃料など“見栄え”の政策より、給食・学童・送迎など実利を優先。
シニア・介護の質を上げる手当て
-
介護士の家賃補助等、**人材確保に効く“現実的な処方箋”**を導入してサービスの質を担保。
行政の規制・制度の見直し
-
財団規制の緩和など、寄付・民間資金の社会還元を妨げる仕組みを改善。
-
**“全ての増税に反対”**を掲げ、既存制度や税制の“歪み”を数字で点検する。
小池都政への厳しい指摘ポイント(論点別)
「二元代表制」の軽視と説明責任
都議会議員として知事との面会すら調整されなかったとする一連の事案に対し、さとうさんは**二元代表制の要諦(知事と議会の相互チェック)の観点から問題提起を続けています。主要会派とは面会しても1人会派は“ハブられた”とされる対応を「民主主義の手続きとして疑問」と批判。都政運営の“選別的コミュニケーション”**に対して、議会人へのリスペクトを求める姿勢を明確にしています。
B. 透明性の欠如(情報公開と意思決定)
本会議の一般質問では、都営住宅等事業の“消費税・長期無申告”という重大論点を筆頭に、補助金の透明性不足や宿泊税見直しの公平性、都立病院での外国人患者の未収金など、意思決定の見える化を求める質問を連発しました。会計・税務の基礎に立ち返る精密な指摘は、都政の“説明責任”に真正面から迫るものです。
たとえば消費税の無申告問題では、「2002年度から2022年度までの長期未申告」「税理士法人の指摘後も期限後申告を怠った疑い」といった時系列の事実関係を精緻に確認し、内部統制の欠陥や隠蔽的体質を質しています。
また、宿泊税の増税論議に対しては、使途の妥当性・公平性(誰からどれだけ取り、何に使うのか)を数字で詰めるよう迫り、増税なき政策運営を都政に求めています。
外国人患者の未収金問題では、総額や補填額の開示にとどまる都の答弁姿勢に対し、在留資格別の把握や徴収体制の強化など、事実に基づく議論を求めています(※同テーマは国でも対策が進む分野)。
いずれの論点も、**「増税より先に、足元の非効率と説明不足を減らすべきだ」**という明快なメッセージにつながっています。
彼女の強み——「数字で詰める政治」
さとうさんの特徴は、“数字の読み解き力”を民主主義の現場に持ち込んだ点にあります。
-
問題の指摘だけでなく、**制度の設計変更(減税特区・インボイス見直しの意見書・支援の中身を厚くする再配分)**に踏み込む。
-
家計に効く具体策を優先し、見栄えより実利を貫く。
-
「行政が“ため込み”、住民は“疲弊”」というアンバランスを会計目線で是正する。
議場・ネット双方の注目を集めた初の一般質問は、その象徴的な瞬間でした。傍聴席が埋まり、都の答弁が**“判で押したようなテンプレ”に見えるほど、質問の勘所(ファクト・数字・手続き)**が鋭かったからです。
小池都政との距離感——「対立」より「統治の質を上げる競争」を
さとうさんの厳しい指摘は、個人攻撃ではなく“都政の統治品質”の議論に収れんしています。
-
会う・説明する・開示する——民主主義の手続きを守るよう迫る。
-
数字に裏打ちされた政策評価を行い、増税より先に無駄・不正を削る。
-
住民の可処分所得を増やす視点で、減税と支援の中身を磨く。
この「統治の質を上げる競争」に、小池都政がどこまで応えられるか。都政の透明性・説明責任のリトマス試験紙として、今後も大きな意味を持ちます。
主要政策のクイックリスト(要点整理)
-
減税特区:千代田発のモデルで、“取り過ぎ”の是正を先導。
-
インボイス廃止の意見書:零細事業者の実負担から出発した制度見直し。
-
区長報酬70%カット構想:**“身を切る改革”**を財源確保の交渉材料に。
-
学童・習い事・シッター支援の拡充:**“時間の壁”**を壊す子育て支援。
-
介護士家賃補助:現場の人材確保に資する実効策。
-
財団規制の見直し:寄付・社会還元の回路を開く。
いま注目したい「3つの焦点」
-
都営住宅特別会計の消費税“長期無申告”
事実関係の確定・責任の所在・再発防止(内部統制)を、議会が監視し続けられるか。 -
宿泊税・受益と負担の見直し
観光振興・地域負担・用途の透明性——“取り方と使い方”の整合が問われています。 -
未収金(とくに外国人患者)への制度対応
「数字」と「医療アクセスの人権」をどう両立させるか。国の対策とも連動して、バランス型の解決策が求められます。
都営住宅等事業会計(特別会計)の消費税「未申告」問題とは
結論と現状
東京都は都営住宅等事業会計(特別会計)について、平成31年度(2019年度)~令和4年度(2022年度)分に消費税の申告・納付義務があったにもかかわらず未申告だったとして、2025年9月22日に計1億3,642万円(うち消費税約1億1,965万円、延滞税約1,079万円、無申告加算税約598万円)を申告・納付したと公表しています。経緯としては、令和5年度分からはインボイス対応で申告・納付を開始していたものの、その前年度分の扱いについて**東京国税局からの照会(令和7年5月)**を受け、義務があると確認されたという説明です。
重要ポイント
・特別会計であっても課税売上高が1,000万円超になれば、通常の「事業者」と同様に申告・納税義務が生じます。都はこの法的建付けを再確認したうえで遡及対応を行った、という位置づけです。
なぜ「住宅関連」で消費税が発生し得るのか
住宅家賃そのものは非課税ですが、駐車場収入や広告・付帯事業収入、売店賃料、再エネ売電収入などは課税対象となり得ます。これら課税売上の積み上がりで1,000万円超に達すると、特別会計としての消費税申告義務が発生します。税理士団体の解説でも、今回のケースをそのように整理しています(※都の公式発表は金額・期間の事実を示し、収益内訳の詳細には触れていません)。
「特別会計」とは何か(基礎知識)
特別会計は、特定の事業を一般会計と切り分けて経理するための会計単位です。東京都は複数の特別会計を持ち、都営住宅等事業会計はその一つ。条例上も、住宅管理費・建設費などの歳出と、住宅等使用料・都債等の歳入を独立して処理する枠組みが規定されています。
さとう都議の問題提起の射程
さとう都議は、「長期にわたる未申告」をめぐり、内部統制・チェック機能、および説明責任の観点から厳しく質しました。都は2019~2022年度分の未申告を認めて納付しており、ここからは(1)事務手続のどこで見落としが生じたか(2)再発防止策の制度化、という実務論へ踏み込むことが重要になります。公表ベースの事実関係(納付額・対象年度)は前述の通りです。
都立病院の「未収金」と外国人患者をめぐる制度対応
まず、未収金はどれくらいあるのか(公式資料の俯瞰)
東京都立病院機構(都の地方独法)の令和5年度貸借対照表では、「未収金」残高が約343.9億円と開示されています(注:ここで言う「未収金」は患者負担の未収金に限らず、広義の未収金を含む会計科目です)。一方、都議会決算特別委員会(令和五年度)では、当該年度に新たに発生した医業未収金は約4.1億円で、**患者負担総額に対する割合は2.6%**に改善した、との答弁も確認できます。
このように、**財務諸表上の広義の「未収金」**と、医業収入に関わる狭義の未収金の年度発生分は、指す範囲が異なる点にご留意ください。
「外国人患者の未収金」をどう把握しているか
本会議のやりとりをまとめた記録・解説では、令和5年度末の過年度未収金残高:約7億0063万円/うち外国人:約1億5377万円、令和6年度末:6億8417万円/うち外国人:約1億7155万円との答弁要旨が紹介されています(在留資格別内訳は「把握していない」との趣旨)。一次情報は議会動画や速記録の公開待ち部分もありますが、質疑の要旨として複数のまとめが一致しています。数字を引用する際は「議会答弁の要旨として報じられた値」である旨を明示するのが適切です。
都の「制度対応」:補てん策・受入れ体制・回収の仕組み
(A)外国人未払医療費補てん事業
都は外国人患者の未払い医療費の一部を医療機関に補てんする制度を持ちます。入院は14日、外来は3日まで、1患者・1医療機関あたり上限200万円。ただしこの制度は**「都が開設者の病院(=都立病院機構等)」は対象外で、主に民間医療機関**を支える仕組みです。
(B)外国人患者受入れ体制整備支援
通訳・標識・会計・多言語化など、受入れ体制の整備費を助成するスキームも走っています。言語・文化の障壁対応を通じて、未収金発生の抑制や診療の円滑化を狙うものです。
(C)都立病院機構の未収金回収フロー
都立病院は発生予防(支払相談・キャッシュレス化・制度案内)と回収促進(速やかな催告・弁護士委任)を車の両輪で運用。実際に法律事務所へ回収を委任する旨を各病院が公表しています。
(D)国のガイダンス
厚労省・研究班の資料でも、訪日外国人は自費100%ゆえ未収金リスクが高い、保険・アシスタンス会社対応やデポジット等の必要性が指摘されています。
さとう都議が迫った論点(要旨)
-
在留資格別の未収金把握:リスク分析と政策効果測定のために、属性別の把握を求める。
-
診療単価の妥当性:自費患者に対する**単価設定(先進国では300%例も)**など国のマニュアルとの整合を問う。
-
補てん・回収スキームの改善:制度の対象・上限・事務負担を再点検し、再発防止と公平性の両立を図る。
まとめ——「増税の前に、手続きと数字を正す」
さとうさおりさんの政治は、**“増税の前に、手続きと数字を正す”**という一点に尽きます。
-
二元代表制の手続きを尊重すること(会う・説明する・開示する)。
-
会計・税務の基礎に立ち返った政策評価を徹底すること。
-
家計の可処分所得を増やすことを第一義に、減税と支援の中身を磨くこと。
小池都政への厳しい指摘は、対立のための対立ではなく、統治の品質向上に向けた健全な緊張関係の表れです。数字に強いローカルリーダーが都政にいることは、都民にとって確かな“資産”だと感じます。

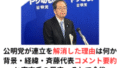

コメント