こども食堂はいつから、なぜ始まったのか
いまや全国で当たり前のように語られる「こども食堂」は、2010年代前半に草の根の実践から立ち上がりました。発祥の一つとして広く知られているのが、東京都大田区の「気まぐれ八百屋だんだん/だんだんこども食堂」です。店主の近藤博子さんが2012年に「子どもがひとりでも来られる低額の食堂」を始め、地域の居場所づくりと食の支援を結びつけたことが、その後の全国的な広がりの先駆けとされています。
きっかけは、経済的困窮や家庭の事情で十分な食事がとれない子どもが身近にいるという現実でした。単なる配食ではなく、「誰もが来られる開いた場」として設計された点が、スティグマ(烙印)を避け、地域のつながりを生む仕掛けになりました。
目的と背景――見えにくい貧困、孤立、そして物価高
こども食堂の目的は大きく三つに整理できます。第一に「食の確保」、第二に「居場所づくり」、第三に「地域のつながりの再生」です。日本の子どもの相対的貧困率は直近の厚労省統計で11.5%。OECD比較でも低くはなく、ひとり親世帯などで課題が根強く続いています。
さらに、コロナ期を経て会食形式は復調した一方、物価高・食材高騰の直撃が続き、運営資金不足や食材不足が上位の悩みとして挙がっています。
どれくらい普及し、どれくらい利用されているのか
認定NPO「むすびえ」の全国箇所数調査(2024年度確定値)では、こども食堂は10,867箇所。公立中学校・義務教育学校の数(9,265校)を上回る規模に達し、**充足率(校区実施率)34.8%という推計も出ています。延べ利用者数の推計は年間約1,885万人(うち子ども約1,299万人)**にのぼります(推計方法は実態調査の平均参加者数に基づく)。
この伸びは、コロナ禍以降に開設が加速したこととも符合します。最新の実態調査でも開始年のピークは2020~2022年で、ここ5年ほどで全体の約7割が立ち上がっています。
現場の実態――誰が、どのくらいのリソースで回しているのか
運営主体は任意団体(市民活動・ボランティア団体)が41.7%で最多、次いでNPO法人16.2%、個人11.5%など。企業や社福法人、自治会等も一定数ありますが、全体としては草の根の市民=ボランティア基盤で支えられていることが数字に現れています(第2回全国こども食堂実態調査)。
費用面では、年間運営費の平均59.3万円(中央値30万円)。活動全体を金銭・物品寄付やボランティア労働まで含めて金額換算した推計では、全国合計で年約73億円規模が現場で費やされています。つまり、行政の外側で、市民が相当の資源を持ち寄って社会機能を下支えしているのが実態です。
開催形態は会食が主流に戻りつつあり、会食形式が8割超。一方でフードパントリーや弁当配布など、多様な形でニーズに合わせた柔軟な運営も一般的です。
国や自治体の支援は何をしているのか
国レベルでは、こども家庭庁が**「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」として、こども食堂や宅食、フードパントリー等を広域で支える中間支援団体**を採択・補助しています。2025年度(令和7年度)公募要項では、複数都道府県にまたがるネットワーク等を条件に掲げ、地域の取組を後方から支援する仕組みが整えられています。
また、衛生面は厚労省の**「子ども食堂の衛生管理のポイント」が参照され、許可・届出はケースバイケースでまず保健所に相談**という運用が基本になっています。
「政府がしっかりしていたら、こども食堂はいらないのでは?」という問い
この問いは感情論ではなく政策論として正面から受け止めるべきだと思います。子どもの貧困率が二桁で推移してきた現実、ひとり親世帯の脆弱さ、物価高の影響などを考えれば、セーフティネット(現金給付、住まい、就労・学習・養育支援)のベースを厚くするほど、こども食堂の“必要性としての役割”は薄まるはずです。
他方、こども食堂が果たしてきた**「誰でも来られる、地域で支え合う居場所」という役割は、たとえ所得再分配を強化しても、公的サービスだけでは代替しづらい価値を持ちます。理想像は、困窮ゆえに“行かざるを得ない”場ではなく、地域の多世代交流拠点として“行きたいから行く”場へと比重が移ることです。現状は、その前段として社会の穴埋め**に多くの市民が自腹と時間で奔走している――そこに政治がどう応えるかが問われています。
子ども家庭庁への言及
前提(現状のファクト)
-
日本の子どもの相対的貧困率は約11.5%(直近公表ベース)。つまり9人に1人規模で、国際的にも低くありません。
-
子ども食堂は全国10,867箇所まで拡大。利用は年間のべ約**1,885万人(子ども約1,299万人)**と推計され、事実上“地域の第三のセーフティネット”になっています。
-
政府は2024年10月から児童手当を拡充(所得制限撤廃、高校生まで対象、第三子以降3万円)。一歩前進ですが、根本の所得・住居・教育・ケアまではまだ届き切っていません。
-
「こども大綱」「こども未来戦略」はあるものの、省庁縦割りの壁と実行力(人員・財源・データ連携)が課題です。
当面:こども食堂の“息継ぎ”を確保(現場が回る最低限)
-
基盤費(固定費)を国が面倒みる
会場費・光熱費・保険・衛生用品・備品を対象に、定額の基盤交付を全国一律で。任意団体が多い実態に合わせ、申請書類を極限まで簡素化。 -
食材ルートの公的連結
学校給食・フードバンク・JA・小売との常設連携を自治体計画に組み込み、物価高局面の食材確保を安定化。(給食無償化の広がりを梃子に、調達を一体設計) -
人の持続可能性
コーディネーター人件費を補助(燃え尽き対策)。ボランティア“善意”頼みの構造を脱却。 -
安全と見守り
保健所連携で衛生ガイド徹底、事故時補償(共済)を国のスキームで用意。
本丸:根本要因に効く「5本柱×15施策」
柱A|所得の底上げ(“足りない”を直撃)
A-1 児童手当の段階的増額と物価連動(インフレに自動追随)。
A-2 児童扶養手当の増額・期中給付化(ひとり親のキャッシュフロー改善)。
A-3 就学援助の国基準化+自動給付(申請漏れ解消)。
A-4 **給付付き税額控除(日本版EITC)**を恒久制度に。
A-5 住宅扶助・家賃補助の常設(家計の固定費を下げる)。
柱B|食と学び(毎日の生活の質を保障)
B-1 学校給食の段階的無償化(国:自治体=マッチング方式、まず中位所得層まで)
B-2 朝食・長期休暇の栄養支援(夏休み・春休みのギャップを埋める配食クーポン)。
B-3 学習支援×居場所(学童・放課後子ども教室の定員拡大/料金軽減)。
B-4 スクールソーシャルワーカー/カウンセラーの常勤配置比率を倍増。
柱C|妊娠期~未就学の切れ目ない支援
C-1 **子育て世代包括支援センター(日本版ネウボラ)**を全市区町村で機能化(努力義務→実質必置へ、財政措置)。
C-2 **ホームビジット(要家庭訪問)**の全国標準化(出産直後~乳幼児)。
C-3 保育の配置基準改善(1歳児・4–5歳児の配置改善を前倒し、職員確保の国費支援)。
柱D|虐待・ヤングケアラー・DVへの早期対応
D-1 こども家庭センターの全国展開と専門職(統括支援員・ソーシャルワーカー)増員。
D-2 24/7相談と一時保護の増床、親支援プログラム(養育困難の軽減)。
D-3 ヤングケアラー支援(家事・介護の外部化サービスを自治体メニューに)。
柱E|データ駆動の司令塔化(こども家庭庁の役割強化)
E-1 こども予算の“タグ付け”(省庁横断で可視化、政策効果を追跡)。
E-2 KPI法定化(英国の“目標管理”に学び、貧困率・欠食率などの数値目標を閣議決定)。
E-3 自治体間格差の是正交付金(成果連動/支援が薄い地域に厚く配分)。
なぜ「現金+サービス」の同時投下がいるのか
-
海外の実証では、現金給付の拡充が子どもの貧困を大幅に引き下げることが確認されています。米国では2021年の拡張CTCが子ども貧困を5.2%(SPM)まで低下させる要因に(翌年に縮小すると再び悪化)。現金が家計の安定・食の確保に直結する好例です。
-
一方で現金だけでは孤立や虐待、発達課題には届き切らない。だからネウボラ型の継続支援・相談・訪問をセットにして、現金+サービスの両輪でいくのが実務上ベストです。
茂木敏充氏の「子ども食堂」訪問――経緯と受け止め
いつ・どこを訪問?
-
2025年9月21日(日)/東京都江戸川区「NPO法人らいおんはーと 365日子ども食堂『ぬくぬく』」。同施設で子どもと交流(食事、けん玉、トランプ手品など)をした後に囲み取材に応じました。
訪問の目的(本人の説明)
-
こども食堂は**「子どもの居場所づくり」であり、家族・地域の“絆”が大切**と強調。現場の実情(食材調達の難しさ等)を把握するための視察だったと位置づけています。
-
自身が掲げる**「数兆円規模の生活支援・特別地方交付金」**の活用先として、こども食堂のような“行政の手が行き届いていない領域”も視野に入れると発言。
-
X(旧Twitter)でも、**「現状等について意見交換」**しに行った旨を投稿しています。
訪問後に何をコメントした?
-
物価高の影響を実感し、**「早急な対策が必要」**と発言。
-
**「子どもたちの笑顔に接することができたことが一番の収穫」**と所感を述べています(囲み取材)。
-
SNSでは、施設名を明示して**「現状の意見交換」や「楽しく迎え入れてもらった」**旨を投稿(同日)。
何を得た(と本人が言っている)?
-
現場の声の把握:食事提供だけにとどまらない“居場所”としての機能、そして食材調達コストなど運営上の負担感。
-
政策の当て先:前述の特別地方交付金を「こども食堂などにも使ってもらいたい」とし、**現金・物価対策を含む“即効性のある支援の必要性”**を再確認したとしています。
-
象徴的な“収穫”:本人は**「子どもたちの笑顔」**を挙げています(※これは評価・印象の言及で、数値や具体策の提示ではありません)。
ネットの反応
-
子ども食堂に来て誕生日を祝わせる構図が逆転している。
-
本来はこども食堂が要らない社会を作るのが政治の仕事では。
-
物価高の尻拭いを地域に丸投げしておいて、現場で笑顔は不誠実。
-
選挙(総裁選)直前の演出に見える。
-
カレーを食べる写真ばかりで、課題を語らない。
-
誕生日は日付的に早いのでは?なぜ今ここで?
-
“居場所”の理念を、**“映える舞台”**に変えるな。
-
「地域の絆」より最低保障を。
-
子どもに歌わせ、ケーキを出させるのは筋違い。
-
支援交付金構想は耳障りがよいが、恒久財源の話がない。
-
食材高騰の現場感に寄り添うなら、給付の即効策を。
-
ボランティアの燃え尽きに目を向けていない。
-
任意団体が過半の現実をどう制度で支えるのか。
-
施設維持費・光熱費は誰が払うのか。
-
会場の無償提供に甘え続ける設計になっていないか。
-
人件費ゼロ前提の支援は持続不能。
-
推計1,885万人利用という規模感に見合う予算を。
-
**「政治家の笑顔」より「寄付の仕組み」**を整えて。
-
衛生管理や保険は現場任せでよいのか。
-
子どもの声を政策に反映した議論がない。
-
学校・学童・福祉の縦割りを超える司令塔が必要。
-
住まい・就労・教育とつながる導線を作れ。
-
データ公開と効果検証をセットに。
-
**「来られる誰もが対象」**という強みを理解していない。
-
**“地方交付金でお茶を濁す”**のではなく法定事業化を。
-
自治体依存の格差を是正せよ。
-
日常的な視察の蓄積がない人ほどイベント化する。
-
現場は寄付より制度を求めている。
-
こども食堂の理念は歓迎だが、貧困対策は別枠で厚く。
-
一方で、「現場に来たこと自体は評価」「寄付や協賛を増やす契機になれば」という少数の擁護もあり。
「見に行く」から「変える」へ――政治と行政に求めたいこと
-
こども食堂の“基盤費用”を制度に位置づけ:会場費・光熱費・保険・衛生用品等の固定費支援を全国一律で。中間支援の交付は有効ですが、任意団体多数という実情に即した簡素な助成・会計スキームが要ります。
-
食材調達の公的連結:学校給食やフードバンク、地元JA・小売と常設連携し、物価高局面での食材確保を安定化。
-
人の持続可能性:ボランティア任せにせず、コーディネーターの人件費を公助で一部負担。燃え尽きを防ぎます。
-
データと評価:実施回数・参加者属性・アウトカムを市町村ベースで可視化。衛生ガイドの普及徹底と事故時の補償枠も整えます。
おわりに――“誕生日ケーキ”が映し出したもの
茂木氏の訪問は、こども食堂が「政治の写真」になる危うさを改めて可視化しました。現場は、貧困や孤立、物価高という構造的な課題の末端で“穴埋め”を続ける市民の努力で成り立っています。誕生日ケーキの光景が違和感を呼んだのは、**「誰のための場か」**という原点を、政治が取り違えたと感じられたからです。
本当に必要なのは、視察の翌日から動き出す制度と予算です。こども食堂が「困窮ゆえに必要な場」から、「地域の誰もが行きたい場」へ比重を移せるかどうか――それは、政治がどれだけ“穴そのもの”を埋めるかにかかっています。

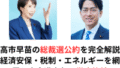
プロフィール|経歴・公約・最近の活動と小池都政への徹底追及を解説-120x68.png)
コメント